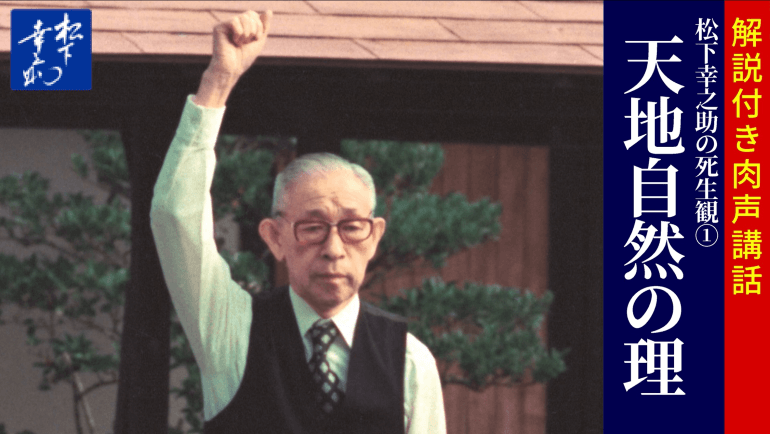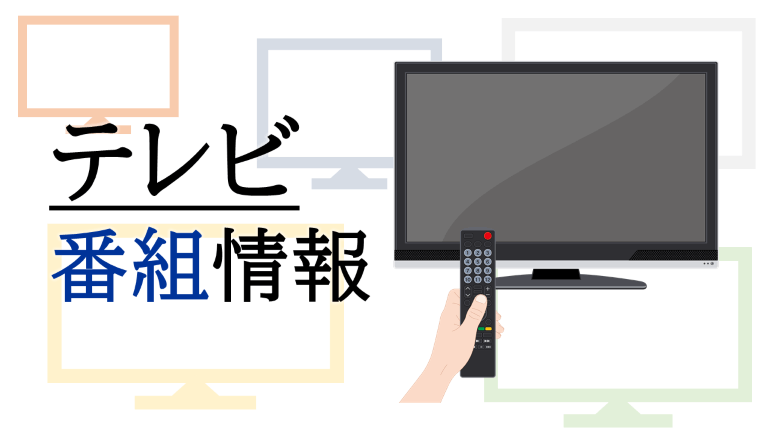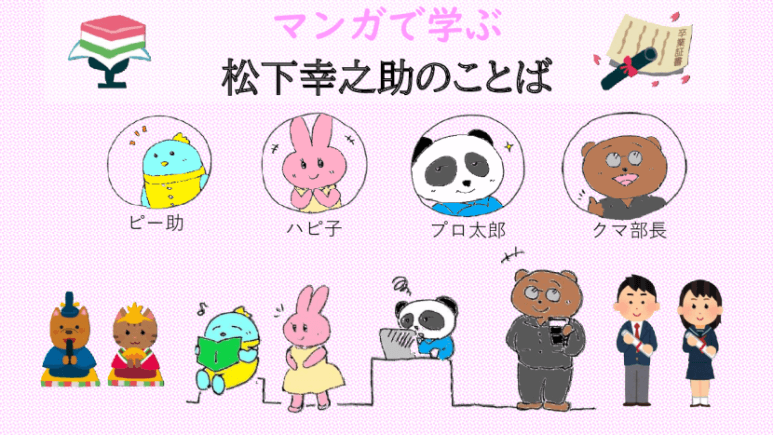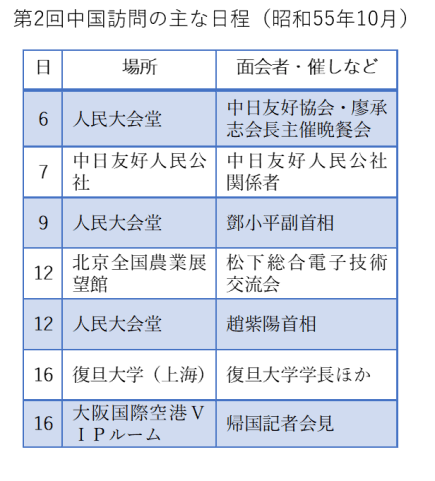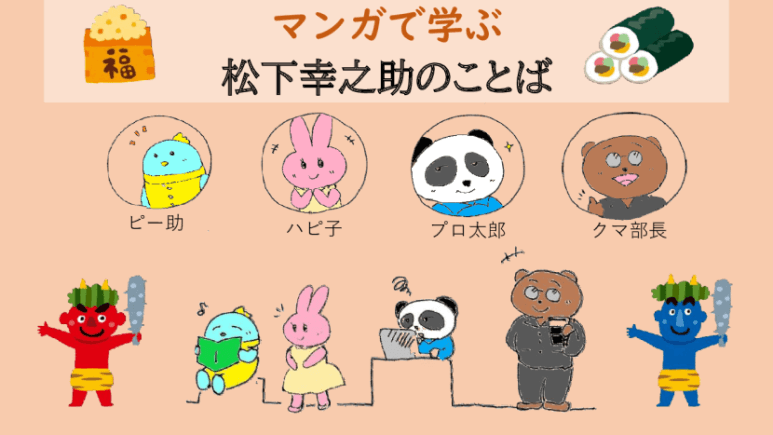池の底というものは、やっぱり汚いものである。水がたたえられてこそ、樹々も映し月も映えるのだが、その肝心の水がなくなってしまったら、映すべき何物もなくて徒(いたずら)に醜い底を露呈するばかりである。湛々たる水面は今はわずかにその面影を残すのみで、周囲には水のあかがつき、ゴロゴロと石が横たわっている。美たちまちにして醜に変ず、である。味気ないことおびただしい。
その醜に変じた池を見ていると、今更のように水の偉大さが身にしみる。池を満たしていた水はただ単に、能もなくたまっているだけではなかったのである。池を満たすという姿が、そのまま周囲に景観の美を添えていたのである。動きもせず、流れもせず、ただ静かに音もなく湛えられていたその水が、実は非常に大きな役目を果していたのである。と同時に、美しいと思っていたその池も、その底はやっぱり醜であったことに気がついた。美の反面には醜がある――そんな思いである。
お互い人間も、これと同じことではなかろうか。美と醜とが相表裏しているところに、人間の真実がある。とすれば、美の面のみにとらわれて、その反面の醜を責めるに急なのは、人間の真実というものを知らないものである。つまり、お互いに暖かい寛容の心をもって接し合うことが、この世の中を明るく暮すための、一番大事なことではなかろうか。
『光雲荘雑記』(1962)