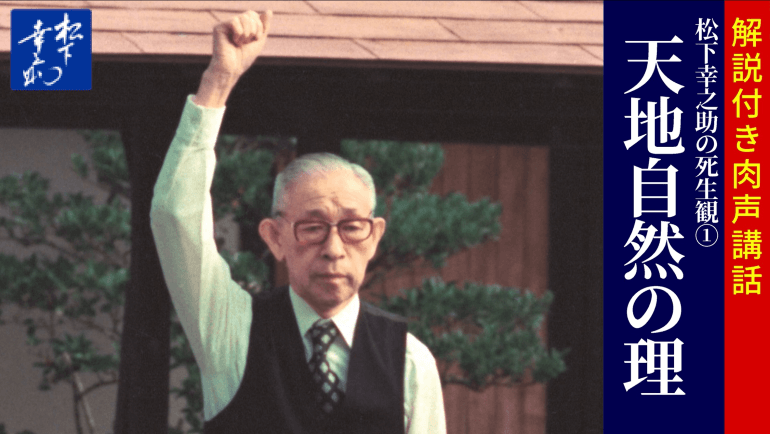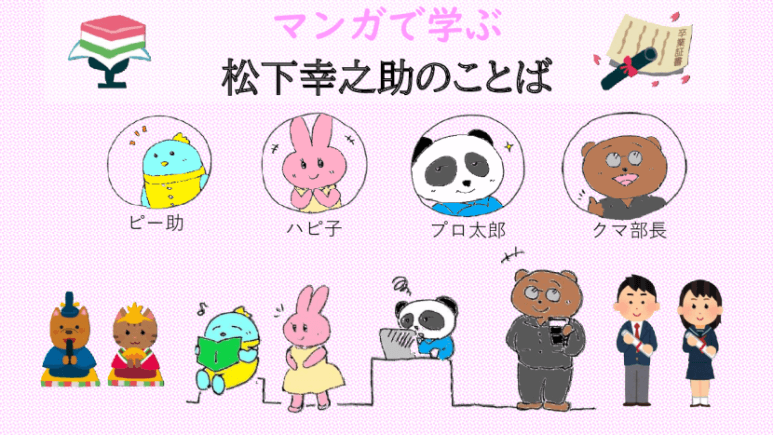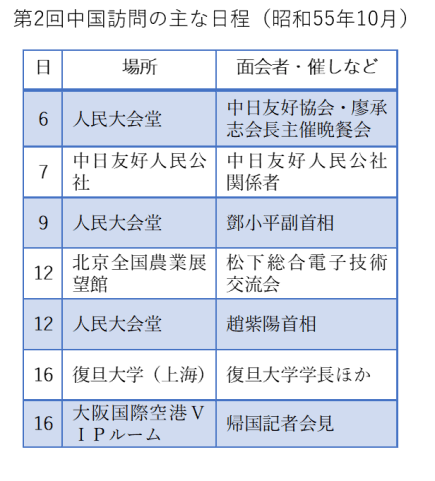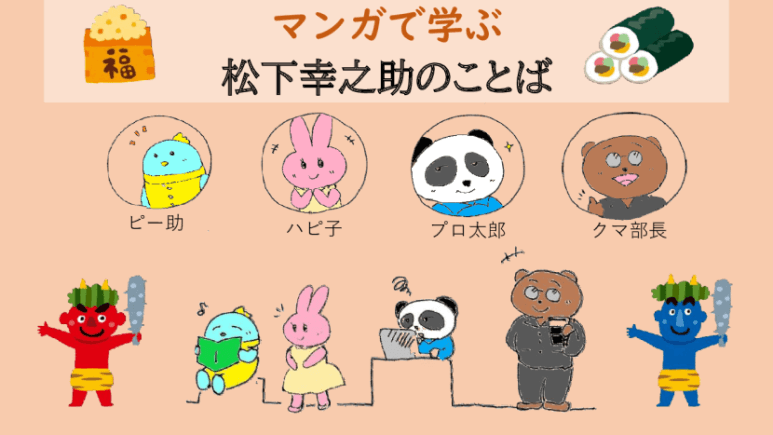親しくつきあっていた製菓会社の社長の長男が、昭和二十五年、三十九歳の若さで急死した。次男、長女もすでに亡くなっており、たった一人残った長男はまさに社長にとっての宝物であった。次期後継者として心に決め、すでに専務の要職につけて期待をかけていただけに、社長の落胆ぶりはひどかった。
葬儀に集まってきた親類縁者たちは、口をそろえて、「あんたは全国に事業を広めているが、すでに六十歳。孫は八歳でこれが成長して事業を行なうようになるまでは、あんたの健康はおぼつかない。大阪の粟おこしのように大阪一円だけに縮小したらどうか」と勧めた。
社長は困りはて、悲報を聞いて駆けつけた親友の幸之助に相談した。
「たいへんだったなあ。これからというときに、まったく惜しい。しかしいつまでもくよくよしても始まらない。やるほか道はあるまい。やりなさい。どんどん事業を進めることが息子さんのためにもいいことなんだ。息子さんもそれを望んでいよう。息子さんの死を乗り越えて、あんたは事業に生きるしか道はないんだ。いいよ、私もあんたとこの重役になろう。出資もしよう。もしあんたが倒れたら、うちの社員を連れて、このわしが加勢に来るからな」
幸之助はそう言って、友人の肩をゆすぶり力強く励ました。社長は、幸之助の友情に心から感謝し、息子の死を乗り越え、事業の鬼になることを心に誓った。