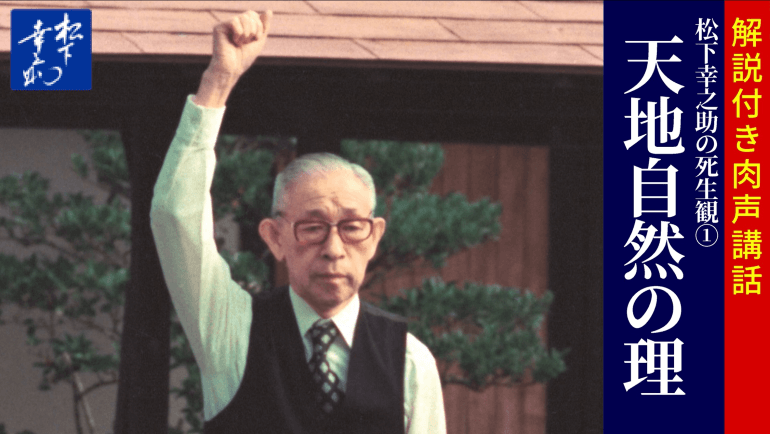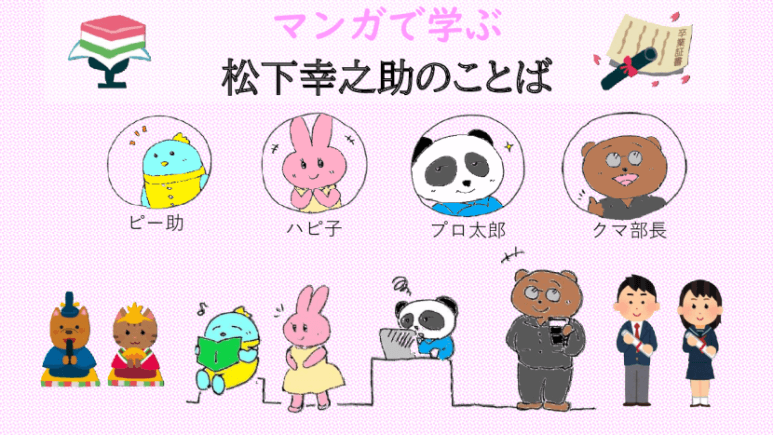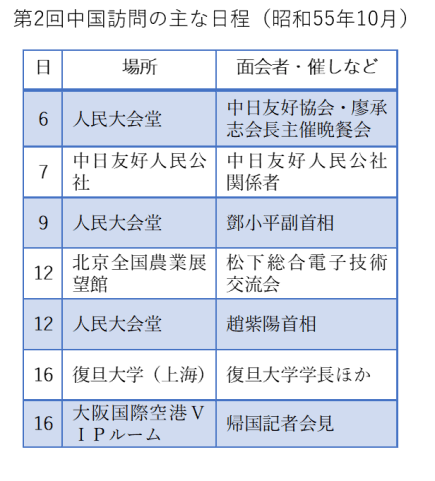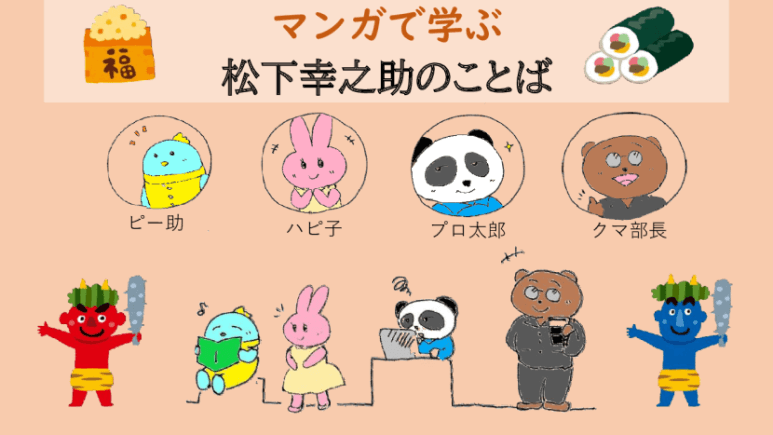昭和二十三年秋。松下電器はGHQから七項目に及ぶ制限を受け、再建もままならず危機に瀕していた。そんななかである日、幸之助は友人の邸宅の一部を借り、在阪の幹部数十名を招いてすき焼きをふるまった。日ごろの慰労ということであった。
会合は、気のおけない内輪の知った者ばかりとあって、にぎやかで楽しいものとなった。が、宴の途中である幹部がふと外を見ると、ひとり幸之助が、庭の築山に登ろうとしている。とっさにあとに従ったその幹部とともに庭の散策を続けた幸之助は、立ち止まってぽつりと言った。
「松下電器も、もうしまいやな」
あまりに意外な言葉に驚いた幹部は、思わず幸之助の手を握りしめた。
「奥様とお二人で始められ今日の松下電器を築きあげられた筆舌に尽くせないご苦労、今のどうしようもない無念さをお察しすると、お気の毒でたまりません」
涙が頬を伝わった。その顔を見つつ幸之助がまたぽつりと言った。
「わしの経営が間違っていてこうなったんとは違うから、ええよ。国の政治が悪かったからや。しょうがないがな」
宴は、幸之助手持ちの色紙や短冊がおみやげとして配られてお開きになった。が、その宴を単純に慰労会と思ってよいのかどうかが、その幹部ののちのちまでの疑問となった。