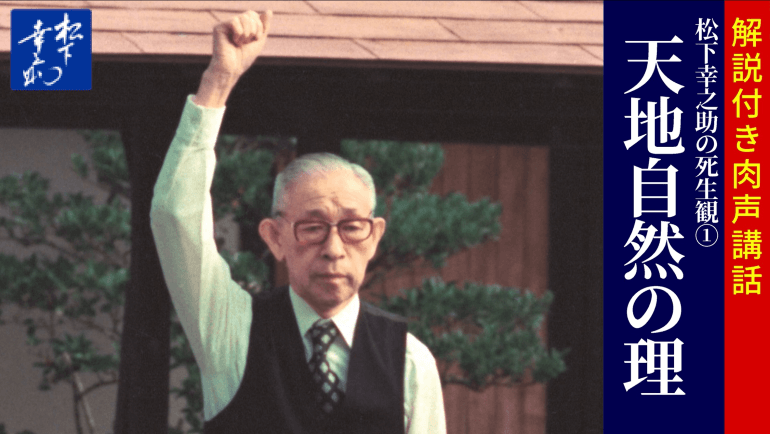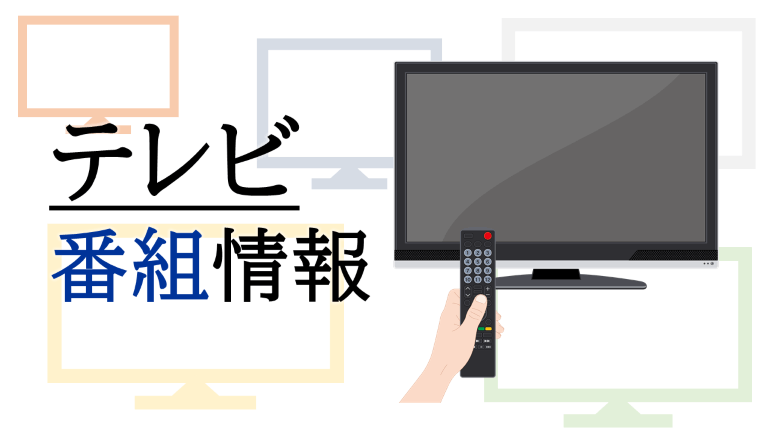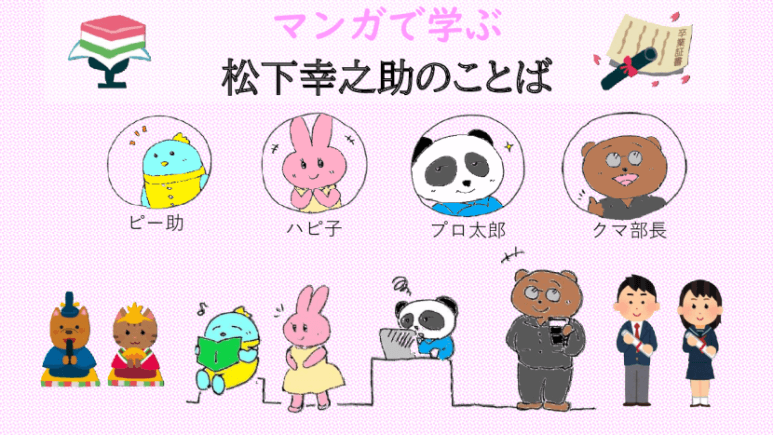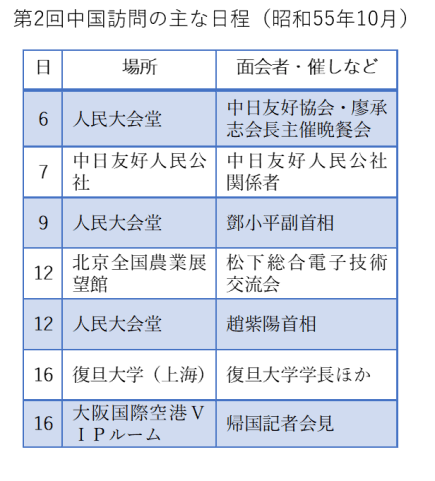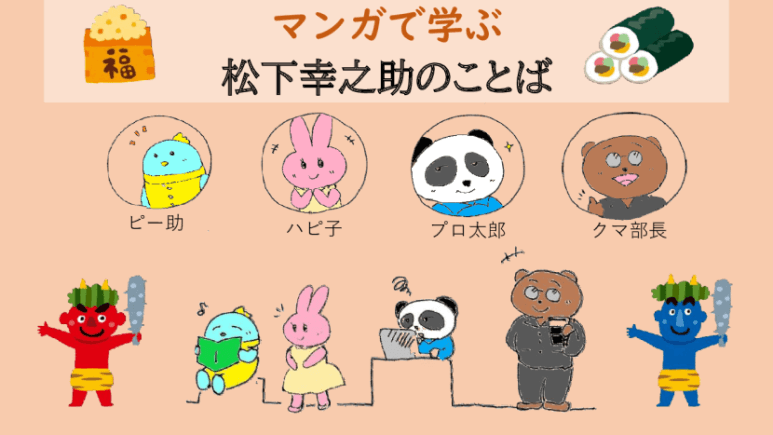第二次世界大戦後の混乱期には、原材料も乏しく、乾電池にも不良が出ることがしばしばあった。
そんなある日、乾電池工場を訪れた幸之助は、責任者から不良が出る状況について説明を受けたあと、不良の乾電池を二、三ダースとコードの付いた豆電球を十個ほど自宅に持ち帰った。
翌早朝七時。幸之助はすぐに来るようにと、電話で責任者を自宅に呼んだ。
責任者が訪れると幸之助は、まだ蒲団の中にいた。その枕元にはあかあかと豆電球をつけた乾電池がずらりと並べられていた。
「これを見てみい。これはきのうきみのところから持ち帰った不良の乾電池やで。きみは、アンペアが低いからあかんと言うとったが、みな直るで」
「社長、どんなにして直されたんですか」
「きみな、物というもんは、じっとこう前に置いて一時間ほどにらめっこしておったら、どんなにしてくれ、こんなにしてくれと言いよるものや。きのう、わしが帰って、飯を食べて風呂に入ってから、前に電池を並べてじっとにらめっこしてたら、"炊いてくれ、炊いてくれ""温めてくれ、温めてくれ"と言うのや。それでコンロで湯沸かしてな、温めたんや」
見ると、確かに、横にコンロと手鍋が置かれている。
「きみら屁理屈ばかり言ってるけど、言うだけやなしに実際にやらないかんのやで。自分の一所懸命につくったものを抱いて寝るくらいの情熱をもって見とったら、それは、必ず何かを訴えよる。わしみたいに電池の理屈をよく知らんもんでも、解決方法が見出せる。きみは何年乾電池をつくってるんや」
「十四、五年でしょうか」
「それだけつくっておって、まだわからんのか。だいたい、電池をつくっておったら、不良が出るもんやと頭から決めてかかってるのやないか。ほんまはな、不良が出るほうがおかしいのや。だから不良が出たらどうするか、どこに誤りがあったのか、よう考えなあかんのや」
責任者は工場に帰ると、すぐ乾電池の製造工程の見直しに取り組んだ。このことがきっかけとなって、ぐっと不良を少なくすることができたのである。