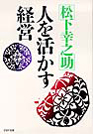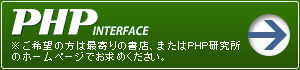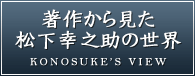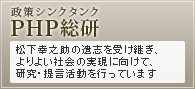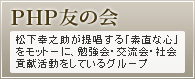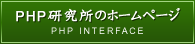HOME > 著作から見た松下幸之助の世界 > マネジメント > 人を活かす経営
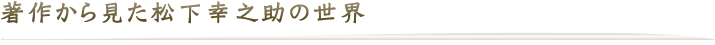
人を活かす経営
【文庫版】目次
| まえがき(旧版) | |
| 序章 人を育て活かすために | |
| 第一章 信頼の経営 | |
| 信頼することの価値 —製法の秘密を従業員に— | 22 |
| 信用の道、商売の道 —初めて東京へ売りに行って— | 26 |
| 熱意が人を動かす —小僧時代に自転車を販売— | 31 |
| 仕事をまかす —若者がひらいた出張所— | 37 |
| 利害にとらわれない態度 —久保田権四郎さんの話— | 42 |
| 相談調が大事 —人を活かす一つのコツ— | 47 |
| 世間というものは —世の中は親切な人ばかり— | 51 |
| 第二章 説得の経営 | |
| 説得なき説得 —将軍家光と阿部豊後守— | 56 |
| 物に説得力あり —幼き日の二つの思い出— | 61 |
| 確信あればこそ —一万個の電池がタダに— | 66 |
| たった一度の訪問でも —区会議員に立候補して— | 72 |
| 私が説得された話 —住友銀行と取り引き開始— | 77 |
| 「信用」を追求する —取り引き開始前の二万円— | 82 |
| 百万言を費やすよりも —一休和尚と地獄極楽— | 88 |
| 満場一致の賛成を —誠意をもってあたる— | 92 |
| 第三章 人間の経営 | |
| 心はどのようにも動く —大激論のあとのふしぎな変化— | 98 |
| 臨機応変に対処する —謙信と毘沙門天— | 103 |
| 心を一つにして —初荷行事で盛り上げる— | 109 |
| 経営をしているか —それができるのが人間— | 113 |
| その気にさせる —明治時代の税務署のやり方— | 117 |
| 人間の尊さを知る —経営は人間が行なうもの— | 121 |
| 決めるのはだれか —松下政経塾と不確実性— | 125 |
| 部下の提案を活かす —とにかく一度やらせてみる— | 129 |
| 六〇%の可能性で —適任者の選び方— | 134 |
| 第四章 自省の経営 | |
| 大将はいかにあるべきか —とことん競争してやるぞと— | 140 |
| 自分を戒めるために —遵奉すべき七精神— | 144 |
| 指導者のあり方 —人を育てる上で大切なこと— | 148 |
| 自分自身への説得 —「運が強い」と信じさせる— | 151 |
| 心の転換をはかる —考え方によって熱も下がる— | 156 |
| 自分の魂を売る —同じ品を安く売る他の店— | 160 |
| 自分の運命に従う —気に病まずに対処する— | 164 |
| くり返し訴える —お互いの心がまえを固めつつ— | 168 |
| 悩んでも悩まない —悩みがあるのが人の常— | 173 |
| 名医になってほしい —早期治療の大切さを説く— | 178 |
| 第五章 信念の経営 | |
| 自分の考えをもつ —実らなかった会議— | 184 |
| 正しいことは通るか —男と男の約束を守ったら— | 190 |
| 日ごろの誠意があればこそ —止められそうになった取り引き— | 195 |
| あきらめたらおしまい —十五万円の無条件貸付— | 200 |
| 成功の秘訣 —うまくいかなかった同業者— | 205 |
| 見方を変える —自分の仕事の意義を考えて— | 210 |
| 決意が人を動かす —ケネディ大統領の態度— | 214 |
| 自信はどこから —何が正しいかを基盤に— | 217 |
まえがき(旧版)
企業経営には、いろいろな事柄が含まれている。製造の問題もあれば販売の問題もある。人事の問題もあれば渉外の問題もある。また、人生、社会的な事柄も含まれている。
しかしながら、そのいずれにしても、結局は人の問題になってくる。経営といい、商売といっても、その内容、あり方を左右するものは、人である。この世の中のすべていっさいは人をぬきにしては考えられない。どのような問題であろうと、人とのかかわりがあるからこそ問題になる。これは当たり前のことである。事業またしかり。経営、商売もしかりである。
だからこそ、われわれは、つねに人間というものを問題にし、その本質を追究していくことが大切になってくる。人間の本質をきわめ、それを実際の各面に活かしていくところに、本当にのぞましい姿が生まれてくるのである。
本書は、そういう人間についての問題を、いろいろな面からとり上げ、具体的な事例にふれて考えてみたものである。こうしたものが、果たしてみなさんのお役に立つかどうかわからない。が、今日のようなきびしい環境においては、とくに“人を活かす”ことが大切になってくるので、私なりに、このような形でまとめてみたしだいである。
ご高覧賜わらばまことに幸せである。
昭和五十四年八月
松下幸之助