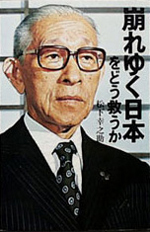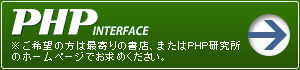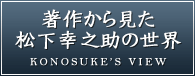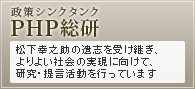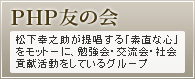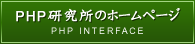HOME > 著作から見た松下幸之助の世界 > 政治と経済と社会について(国家観) > 崩れゆく日本をどう救うか
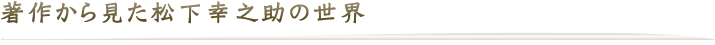
崩れゆく日本をどう救うか
目次
| まえがき | ||
| 序 かつてない事態 | ||
| 不況下のインフレ | 12 | |
| 物をかかえて苦しむ | 15 | |
| イタリアの二の舞 | 19 | |
| 第一部 沈没寸前の日本 | ||
| 一 | 日本総赤字 | |
| 石油値上げとインフレ | 26 | |
| 世界に独禁法があれば | 30 | |
| 東京の物価は世界一 | 34 | |
| インフレ下の企業経営 | 38 | |
| 輸出がとまれば | 41 | |
| 長年のツケをはらう時 | 45 | |
| 二 | 不信、不平、不満 | |
| 川下で争う日本 | 50 | |
| 不信感が物価を上げる | 54 | |
| 失われた自主性 | 60 | |
| 政府にも力はない | 64 | |
| だれが文化生活を生むのか | 69 | |
| 青年の不満が世界一 | 72 | |
| 三 | 民主主義のはきちがえ | |
| 民主主義はきびしいもの | 78 | |
| 憲法を考える | 82 | |
| 自分の社会的責任 | 86 | |
| 日本の子は日本語を話す | 89 | |
| 四 | 日本はどこへ行く | |
| 世界と日本の国家意識 | 94 | |
| 兄弟で争っても | 96 | |
| 国民を甘やかしてきた政治 | 99 | |
| ケネディ大統領の見識 | 101 | |
| 哲理が欠けている | 104 | |
| 第二部 日本を救う具体策の一例 | ||
| 一 | 覚悟はよいか | 112 |
| 教育過多症の日本 | 114 | |
| 大学多くして不満ふえる | 117 | |
| 東京大学をなくしたら | 121 | |
| 死傷者は中年の主婦 | 126 | |
| 先生の所得倍増を | 132 | |
| 三百万円の雇用費を | 136 | |
| 二 | 物価安定と経済健全化への道 | |
| 臨時物価安定法 | 144 | |
| 輪入物資の場合は | 148 | |
| 経済安定国債 | 152 | |
| 国費を二十%節減 | 155 | |
| 公共企業を黒字経営に | 159 | |
| 日本を世界の“聖地”に | 162 | |
| いまこそダム経営を | 169 | |
| 道は無限にある | 172 | |
| 筆をおくにあたって | 176 | |
| あとがき | ||
まえがき
最近の世情を見ていると、このままでは日本はゆきづまってしまうのではないかという気がしてならない。というより、もうそのことは火を見るより明らかだという感じさえする。ひとり私だけでなく、多くの人がしだいにそういう感じを持ちつつあるようである。みんなだんだんと心配してきたようだし、中にはうろたえる人も出始めている。
昨年の石油危機の時も、個人といわず政府といわず、企業といわず日本国中がみなうろたえた。しかし、このままでいけばもっと大きな混乱が起こるかもしれない。今日すでに政治、経済のゆきづまりは、いわばその極に達しつつあるように思われるが、いまのままでは、日本はあらゆる面でゆきづまってしまうだろう。そのような一大難局にいまお互いは直面しているのだと思う。
だから、このままではいけない。いまのままで手をこまねいていれば、お互いに破滅してしまうほかはない。なんとかこの難局を切りぬけて、そこからよりよい日本をつくりあげていかなくてはならないと思う。
そのためには、いろいろな方策が考えられるだろう。政治、経済、教育その他国民生活のあらゆる面において抜本的な改革がなされなくてはならないと思う。本書は、そうした改革を行なっていくために必要と思われる考え方と、二、三の具体的な方策を私なりに考えて記したものである。
私はもとより一経済人にすぎず、政治なり教育などについて専門的な知識は持たない。だから、内容には、あるいは当を得ていない点、考えの及ばない点もあろうかと思う。ただ、本書はあくまで、なんとかしてお互い国民共同の力でこの一大難局を切りぬけていきたいと考え、その目的で書いたものである。そうした微意をお汲みとりいただき、ご一読の上、それぞれのお立場で難局打開の道をお考えいただければ幸いである。
昭和四十九年十二月
松下幸之助