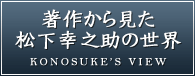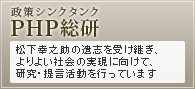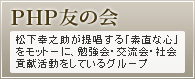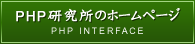アベノミクスによる日本経済復活のカギとなる「賃金」。 かつて「高賃金・高能率」を経営方針に掲げた松下幸之助は、どのような「賃金」観をもって経営にあたっていたのでしょうか。
失敗を自らの成長の糧にする。誰もが思うように、松下幸之助もそうありたいと願いました。成功すればそれは運のおかげ、失敗は自分のせいと考え、事あるごとに反省をくり返しました。さらには成功のなかにも、小さな失敗があると考え、その失敗をも自らに生かすよう心がけたのです。
頻発する食品・食材の偽装表示。
この「偽装」を取り締まる法律といえば不正競争防止法です。
意図的な偽装は「不正」競争を横行させる経営活動なのです。
松下幸之助は市場競争のなかからイノベーションが生みだされると認識していましたが、その競争はあくまで「正しき闘争」でなければならないと社員に強く訴えていました。
自然災害の恐ろしさを実感せざるをえない状況が続いています。
松下幸之助は、自らの経営においては、被災すれば「こけたらたちなはれ」の気概でその対処・対策に臨み、被災された取引先や顧客には、できるかぎりの援助をする姿勢を大切にしましたが、国家・政治への憂国の提言も数多くしていました。
(2013.10.25更新)
2020年のオリンピック開催地が東京に決定しました。1964年以来、じつに半世紀以上の月日が流れたことになります。そのころの松下幸之助はというと、1961年に松下電器(現パナソニック)の社長を退き、自らの思想・哲学の深耕に精を出しはじめていました。しかしこのオリンピック開催という、経済拡大を期待させる国家的イベントに日本が沸き立ったころ、松下幸之助、さらには日本の家電業界は、厳しい経営環境に晒されていたのです。
熱中症の危険が他人事ではない、誰もがそう思うほどの猛暑が続いています。(2013年8月25日時点)
自己の「健康」にいっそうの配慮が必要です。
松下幸之助は生来虚弱の体質だったこともあり、「健康」は常に、やむを得ない関心事でした。そして「弱い人は弱いままで健康である」という独自の健康観をもつに至ります。
ようやく世界遺産に正式登録された「富士山」(2013年7月25日時点)。 日本人にとって、この古くから信仰・崇拝の対象でもあった「神の山」の名を、松下幸之助はしばしば、口にしています。 一つは当然ながら、「観光資源」としての活用を説くときにおいて、でした。 「観光立国」のすすめを、昭和20年代後半から世に問うていたのです。 そしてもう一つは、「ものの見方・考え方」について語る際の「喩え」として、でした。
いまの日本に喫緊に必要とされるのは実体経済の力強い成長です。それは、国家全体の努力により「利益」を生み出すことが必要だということです。
具体的には、より利益を生み出す成長産業に、人材や投資がスムーズにシフトしていくよう、国家がアシストしていくことなどが挙げられることでしょう。
しかしその実現という面でまだまだ疑問符がつくのが、アベノミクスだといえます。「利益」を生み出すとはどういうことか。「利益」に対して企業はどうあるべきか――。
松下幸之助は「利益」について、確たる信念をもっていました。
アベノミクス効果で、ドル高円安トレンドに転換し、日経平均株価も上昇、日本経済が回復の兆しを見せはじめています(2013年5月27日時点)。しかし新たな策にはリスクがつきものです。今後の経済・市場動向を、国民はいっそう注視していかねばなりません。
アベノミクスでは、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略の3つが柱となっていますが、松下幸之助はかつて日本経済の繁栄のために、「株」というものに目をつけ、その活用についての政策提言をしていました。
日本国民にとって悲しい記憶となったあの「3・11」以後も、各地で地震等による災害が断続的に発生しています。東日本大震災(2011)からの復興・再生とともに、新たな災害への対策が国内政治の喫緊の課題となっています。
松下幸之助が遭遇した最大の人災といえば太平洋戦争でしたが、最大の自然災害は、戦前の関東大震災(1923)であり、室戸台風(1934)でした。
それではこの「震災」というものについて、松下はどう考えていたのでしょうか。
(2013.4.25更新)