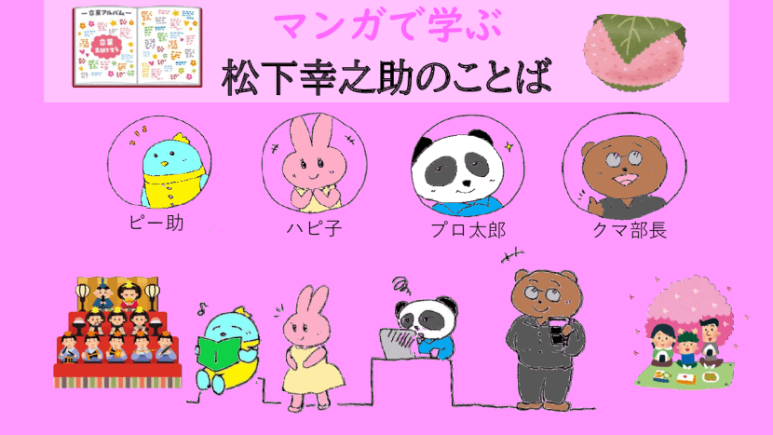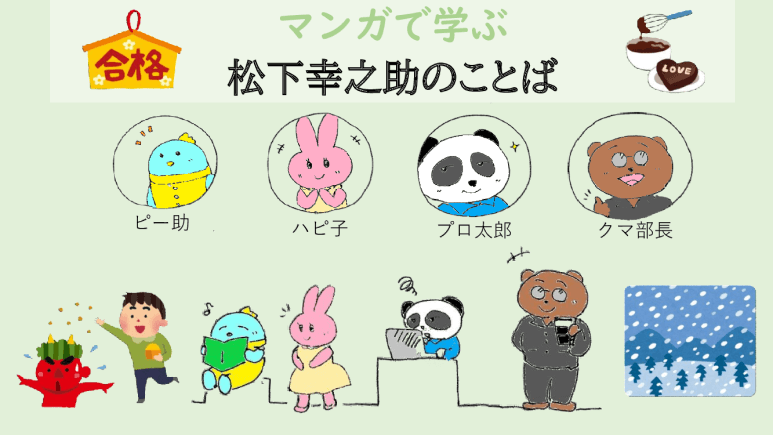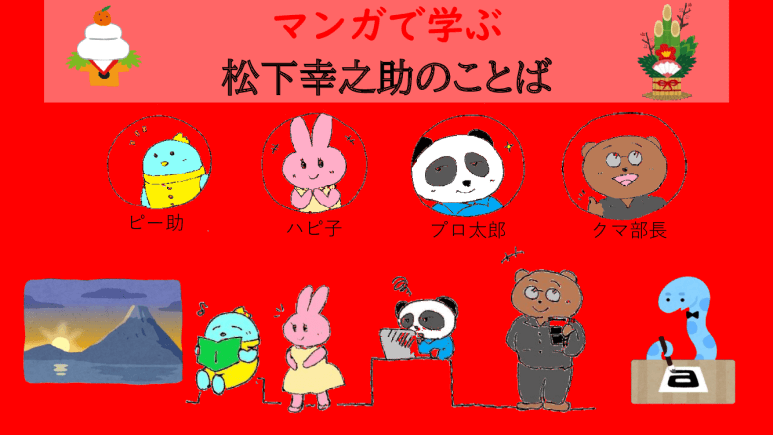2020年のオリンピック開催地が東京に決定しました。1964年以来、じつに半世紀以上の月日が流れたことになります。そのころの松下幸之助はというと、1961年に松下電器(現パナソニック)の社長を退き、自らの思想・哲学の深耕に精を出しはじめていました。しかしこのオリンピック開催という、経済拡大を期待させる国家的イベントに日本が沸き立ったころ、松下幸之助、さらには日本の家電業界は、厳しい経営環境に晒されていたのです。
詳細
2020年の東京オリンピック決定は、現在、改革策に決定打を欠くアベノミクスにとってチャンスの種となるのでしょうか――。今後の自民政権の舵取りに大いに期待したいところですが、こうしたときに歴史を教訓にするのも意義あることでしょう。
東京オリンピックが開催された1964年当時の日本経済をふり返ると、およそ2年前から好況期に入り、オリンピック終了後、まもなく不況に陥るという経験をしています。いわゆる証券不況です。そして1965年には、戦後初の赤字国債を発行せざるをえない状況にいたります。それまで急成長を遂げて日本経済を牽引してきた家電業界も、1959年春の皇太子殿下ご成婚、1962年後半からのオリンピック景気といった好材料がありながら、その成長度合に陰りがみえはじめていました。そうした時代の流れのなかで、1964年の夏は、松下幸之助、いや松下電器にとってひどく暑く、長い夏だったことでしょう。のちに世に知られるようになる全国販売会社代理店社長懇談会、いわゆる「熱海会談」を開いたときだったのです。
当時松下はすでに会長に退いていましたが、事態の深刻さを察知していました。金融の引き締めによる需要停滞などを見据えて、1963年度の経営方針発表では、経済変動に動揺しないだけの体質改善・強化をはかることを社員に強く要望、しかし市況悪化の影響は避けきれず、半期で減収減益という状況に陥りました(それは戦後の1950年の再建時以来のことでした)。さらには販売会社や代理店の多くも赤字経営に落ち込み、「熱海会談」開催にいたります。
松下は、参加した社長たちと直接議論を重ねるなかで、危機の本質をつかみ、最後には松下電器の責任を認め、すぐさま対策を講じます。営業本部長代行として第一線に復帰、販売制度の改革を成功させるのです。まさにその陣頭指揮をとっていた翌1965年度の経営方針発表の場では、オリンピックにふれつつ、以下のように述べています。
今日、世界的に産業界は競争しつつあります。国と国との産業が競争しております。また国内にありましても競争いたしております。みなその競争に打ち勝とうとしているのであります。その打ち勝とうとするところに熱意がこもりまして、創意工夫が生まれ、発明が生まれ、新製品が生まれ、世の進歩が生まれておるのであります。各国間の競争というものが、無理なものでなければ、そこに人類の進歩と申しますか、世界産業界の発達というものがあり、国家またしかりであります。そういうことを考えてみますと、競争それ自体がわれわれの仕事である、と申していいと思うのであります。
昨年、オリンピックが日本で行われまして、各国がそれぞれ熱意を傾けて競技に打ちこんだのであります。競技には、負けるところもあれば勝つところもあるわけですが、やはり熱心に訓練をした選手、それも単なる熱心さだけでなくして、工夫して効果的な訓練法を見いだしたところが主に勝利を得ております。そういう点において、日本のスポーツ界は非常に進歩したものだ、という感じがしまして、私は日本国民のもつ素質に対し、新たに認識を深めました。同時に、日本人としての誇り、自分自身が日本人であることに対して非常な感激を覚えたのでありますが、そういうような競争があってこそ、あの光輝あるオリンピックというものが、世界の人々の感激のもとに行われたと思うのであります。
われわれの日常の仕事もやはりそれと同じことであります。よりよき物をつくって、それを顧客に提供し、そして国民生活をより高くしていくことに、お互いが選手たらんとしておるのであります。そこには苦しいこともありましょう。ある場合には、夜を日についでやらなくてはならないという場合もありましょう。しかし、そういうことに苦痛を感ずるよりも、生きがいを感ずるというようなことでなければならないと思うのであります。あたかもオリンピックの選手と同じことだと思うのであります。われわれはやはり産業のスポーツマンです。そういうように産業界というものが見直されなくてはならないし、本来がそうあるべきものだと思うのであります。
『松下幸之助発言集23』
また10年後に刊行された『経営心得帖』(1974)においては、「プロの自覚」と題して、こう記しています。
以前に『闘魂の記録』といって、東京オリンピックを前にして、選手の人々がいかに練習をしているかを描いた映画を見たことがありました。どの競技も、きわめて厳しい練習で、選手の人々が歯をくいしばりつつ、それに取り組んでいる姿に大きな感銘を受けたものです。特に、女子バレーボールで優勝を遂げたニチボーチームの練習の、悲惨とも残酷ともいえるような激しさには、それこそ度肝を抜かれるような驚きを覚えました。そして、こういうところにオリンピックが光彩を放ち、見る人をして感動せしめる大きな力があるのだなということを感じたのでした。
しかし、考えてみると、オリンピックの選手はみないわゆるアマチュアの人ばかりです。もちろん、国家の栄光を担って技を競うのですから、それだけ真剣みも増すのでしょうが、それにしても、みなそれぞれに本業をもった上での、いわば余技だと思います。ひるがえって、われわれの商売というものを考えてみますと、これはいうまでもなく本業です。アマチュアでなくプロなのです。とすると、アマチュアの人が余技に打ちこむ以上に、自分の本業に打ちこまなくてはウソだとはいえないでしょうか。いささか厳しいいい方をすれば、本業に全身全霊をささげて、そこに喜びが湧いてこないというようなことでは、その本業から去らなければならないという見方もできると思います。能力の問題ではありません。それに全身全霊を打ちこむ喜びをもつかもたないかの問題です。
力が及ばない、という人はたくさんあると思います。しかし、及ばないなりに一心に打ちこむならば、その姿はまことに立派なものがあると思うのです。そういう姿が、人に感銘を与え、人を動かすことになります。そこに知恵と力とが集まって、成果を生むことができるようになってきます。ところが、そういうものがなかったら、いくら力があったとしても、それだけにとどまって、大きな成果はあげられないと思います。ですから、そういう意味で、本業に全身全霊を打ちこんで、なお興味が湧かないというのは許されないことだといえましょう。非常に厳しいことをいうようですが、特に責任者の立場にある人は、こうした点についても自問自答していく必要がありはしないかと思うのです。
この東洋の魔女といわれた女子バレーボール・チームの選手が、自分自身をムチ打ってボールと闘う気迫に、松下は映画をみた夜はなかなか眠れなかったと述懐しています。オリンピックで活躍する日本人をみて、自らが「産業のスポーツマン」となることに生きがいを感じる。また、アマチュアであるオリンピック選手が厳しい練習に取り組む以上に、プロであるお互いが自分の仕事に打ちこまなくてはウソだと認識し、本業に全身全霊をささげる。松下がいうような、そうした日本人の姿が2020年の日本社会に満ち溢れていることを期待したいものです。
PHP研究所経営理念研究本部