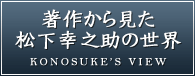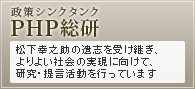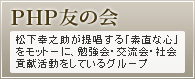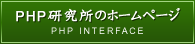自らが創設したPHP研究所が30周年を迎えた昭和51年、松下幸之助は、21世紀初頭の日本はこうあるべきだ、こうあってほしいとの願いをこめて『私の夢・日本の夢 21世紀の日本』という本を出版しました。それは未来小説という体裁をとっていますが、いわば松下幸之助の提言の集大成ともいえるものでした。
松下幸之助が描いた「理想の日本」「理想の日本人」とは、いったいどんなものだったのでしょうか。
日本や世界の物心両面の繁栄を願った松下幸之助は、月刊誌『PHP』をはじめとする各種雑誌や書籍などで、国家や社会に対するさまざまな大胆な構想を発表しました。その根底には、常に世のため人のためを考える「公」の視点と、「なぜ」という問いかけを繰り返すことによって生まれる本質的な問題提起、そして100年単位で物を考える発想力がありました。
ここではそうした松下幸之助の現代にも通ずる主な提言をご紹介します。
提言の詳細はリンク先をご覧ください。
経営は人間が行なうものであり、人間が幸せになるために行なう活動である――。 そう信じた経営者・松下幸之助にとって「経営力」とはどのようなものだったのでしょうか。
(2014.9.25更新)
日本国憲法が公布された1946年11月3日に、松下幸之助はPHP研究所を設立しました。 その後の松下にとって、憲法のみならず、「法」は常に関心事であり研究・提言の対象でした。
「任せて任せず」。 松下幸之助のマネジメントの基本姿勢です。その実践に欠かせない、部下とのコミュニケーション・ツールとして、松下は「電話」を大いに活用しました。
LINEなどメッセージアプリの参入により、熾烈な競争を繰り広げつつ、ますます進化し続ける電気通信事業――。松下幸之助が生きた時代の最新の情報伝達手段といえば、固定電話でした。
毎年5月は、新しい環境に慣れつつも、期待と不安が交錯する毎日を過ごしている方も多いことでしょう。これからどんな運命が待ち受けているのか――。松下幸之助は運命論者ではないと言いつつ、一方で人間の「運」の強さというものを重視していました。
桜が咲き、舞い散る季節は、昔から「春眠暁を覚えず」というように、身も心も緩みがちな時期でもあります。心を引き締め、日々の生活習慣にも一層気をつけ、仕事・学業に臨みたいところですが、松下幸之助はどのように日常を過ごしていたのでしょうか。
これからの日米関係はどうあるべきか――。 松下幸之助が生きた時代、アメリカは日本にとって、戦勝国であり、目標であり、最重要国家でしたが、松下自身はアメリカをどう視ていたのでしょうか。