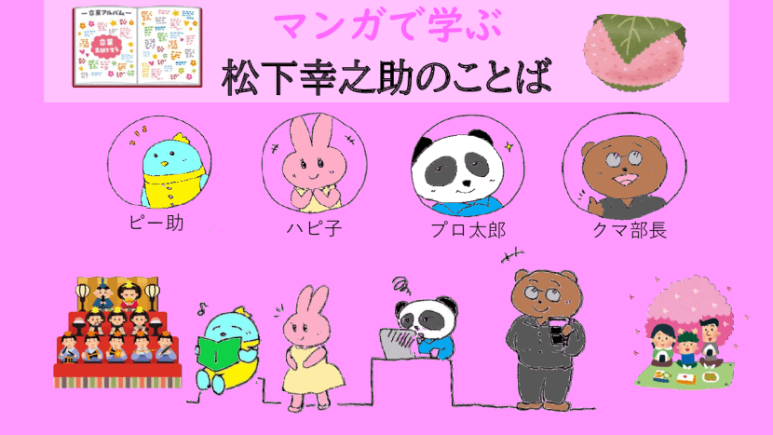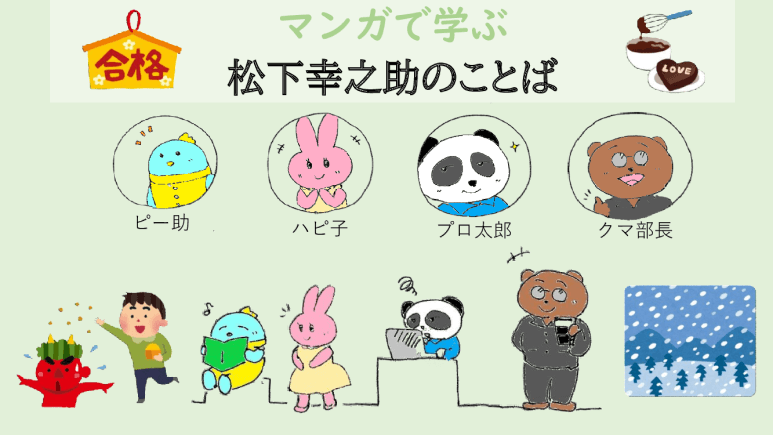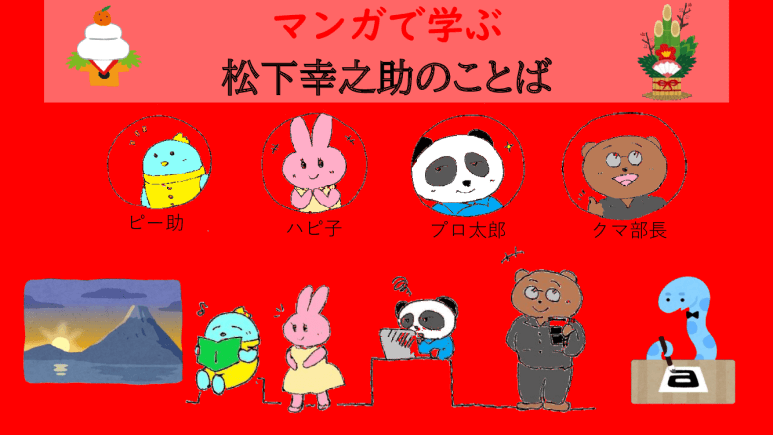アベノミクスによる日本経済復活のカギとなる「賃金」。 かつて「高賃金・高能率」を経営方針に掲げた松下幸之助は、どのような「賃金」観をもって経営にあたっていたのでしょうか。
詳細
91歳の松下幸之助が、PHP研究所主催の経営セミナーに突然顔をだし、短い講話をした際、受講者から「人生のなかで、いちばん嬉しかったことはなにか」と尋ねられたことがありました。松下はそのとき、「丁稚奉公をして、はじめて5銭白銅貨をもらったこと」だと答えました。9歳から奉公生活をせざるを得なかった境遇のなかで、松下は自らの働きに対して報酬が得られるということに大きな喜びを見いだしたのでした。
その後、独立開業し、経営者となった松下は「高賃金・高能率」というすこぶる明快な経営方針を掲げるようになります。戦後の1946年の経営方針発表会でもその徹底を宣言、「高能率を先行せしむるのでなく、高賃金を与えることにより生産意欲を盛りたててやっていくようにしなければならぬ」「これでなおかつ、能率が上がらないときは、団体の会社としては立ちいかず、個人としての生活も破壊されるのであり、これが果たされることにより更に高賃金が約束され、高能率・高賃金が成功するのである」といった賃労働に対する自身の見解を明らかにしています。
しかしその松下が、「賃金」に関して全従業員に詫びなければならなかったときがありました。松下電器が瀕した最大の苦境期、1948年10月のことです。社会の混乱に巻きこまれ、資金繰りも悪化、所定の給料日に支払いができず、分割払いをしなければならなくなったのです。
「まず第一に申しあげねばならず、かつそれについてぜひともご了解を願わなければならないことは、本月の給料の支払いが所定の給料日に全額お支払いできなくなったことである。まことに全従業員諸君に対して申しわけないことであると、私は恐縮いたしている。本月は約5割を所定の日に、残りは11月の10日までに分割払いいたしたい。松下電器が創業してから30年、その間〈かん〉資金につまったことなしとはしないが、所定の給料日に給料の支払いができなかったというようなことは、かつて一度もなかった。その松下電器が今日皆さんに非常に迷惑をかけねばならないということは、私としてまた会社として、心から遺憾と考える。けれども何としても金繰りの都合がつかないので、本日皆さんにその事情を打ち明けたいと思うのである」
(『松下幸之助発言集25』より)
冒頭にこう謝罪し、松下は自社が困難に陥った理由を、社会的背景・経済情勢、さらに市場の混乱といったことに触れながら懇切丁寧に説明します。その上で断じて悲観せず、いまこそ団結し、切り抜ける覚悟をもとうと従業員の士気を鼓舞し、社員にいっそうの努力を要望したのです。それから約20年後の1967年、松下は、5年後に欧州の企業を抜いてアメリカの賃金に近づけると明言し、それを実現しました。
現下の日本経済は、2%のインフレ目標、そして賃金引き上げを掲げるアベノミクスによって、復活の兆しが見えはじめているものの、疲弊した地方経済や多くの中小企業経営は未だその効果が及んでいないのが実際のところです。自動車や建設といった業績好調な業界もありますが、相変わらず厳しい経営状況を強いられている業種・業態もあります。しかしそうした厳しさは、程度や質に多少の差はあっても、いつの時代にも存在するものなのです。1974年に刊行された松下の『経営心得帖』には、以下のように記されています。
最近は、経営や商売をとりまく情勢というものが、ますます厳しくなってきました。一方では、大幅な給与の引上げを行なっていかなくてはならない。それに加えて、原材料などの物価騰貴ということもあります。そういう中で、自分の製造販売している商品については安易な値上げは許されない、できるかぎり現在の価格を維持していく、場合によってはそれを値下げしていく、そういうことが社会から要請されているわけです。したがってお互いの経営なり商売においても、できるだけムダを省き、効率を高めて、生産性の向上をはかって、内外のさまざまな要請にこたえていかなくてはならないと思います。
(上掲書より)
そして賃金を(正しい価値判断のもと、社会の承認を得られるだけの適正な範囲において)増大させ、社会全体の消費力を高めることに貢献していくことを、産業人の使命として受けとめていた松下は、その実践がけっして無理なものではないことを世の経営者に説きました。
同じ情勢の中で、みな同じように困っているかというと決してそうではありません。ある企業は、2割なら2割の賃上げをしても、それを生産性の向上でカバーして悠々とやっている。一方は四苦八苦している。ある商店では比較的安く売っているけれども、利益は適正に取っているのに、別のところでは、高く売っても利益があがらない。そういったことが同じ業種の中でもしばしば見られます。
どうして、そういう差が出てくるのでしょうか。それはひと言でいえばその必要性を感じていた、察知していたということではないかと思います。来年はこれだけ給料を上げなくてはならないだろうから、それだけのものを合理化しておく必要がある、ということで、賃上げを実施するまでに、全部それを吸収してしまっている。だから、大幅な賃上げをしても十分利益があがるわけです。ところが、ともすると、賃上げをしなくてはならないからやった、それで利益が少なくなった、これはたいへんだといって、合理化に取り組んでいくというのがまま見られる姿ではないでしょうか。そのようにあとからやったのでは、それだけ犠牲も多くなってしまいます。やはり、経営というものは、どういう事態が起こってくるかをある程度予見して、それまでに必要な対策を立てて静かに時機を待つということでなくてはならないと思うのです。
もちろん、そういうことの必要性はどこでも一応は感じているでしょう。にもかかわらず、そこに差が出てくるということは、感じていても実行力を欠くといいますか、いいかえれば感じ方にもうひとつ真剣さが足りないということではないでしょうか。経営というものは、単に利口であるとか、頭がよいとかいうだけでうまくいくものではないと思います。やはりそこに命をかけるというほどの真剣さがあってはじめて、何をいつどうしなければならないかというカンもはたらき、それを行なっていく力強い実行力も生まれてくるのではないでしょうか。
(同上)
非常に厳しい要望なのかもしれません。企業の賃金政策には、個々の経営体質だけでなく、社会情勢や業界の体質、時代性や国民性といった要素が複雑に絡みあうからです。しかし兎にも角にも、ともに働く従業員の「賃金」引き上げに、誠実に向きあう姿勢、命を懸けるほどの真剣さを、松下はどの経営者にも要望したのです。
PHP研究所経営理念研究本部