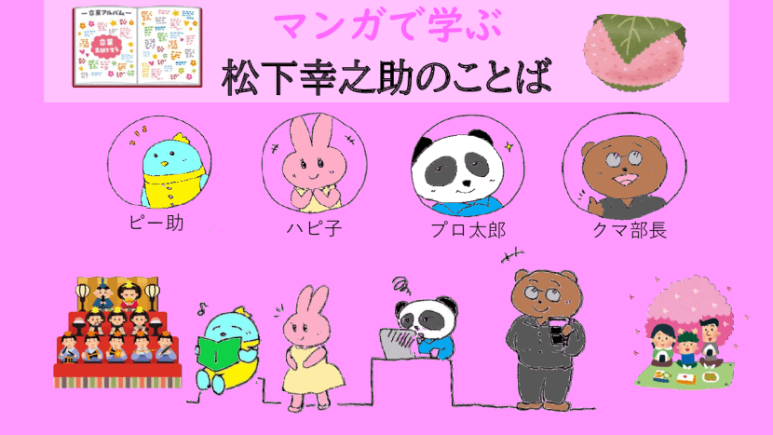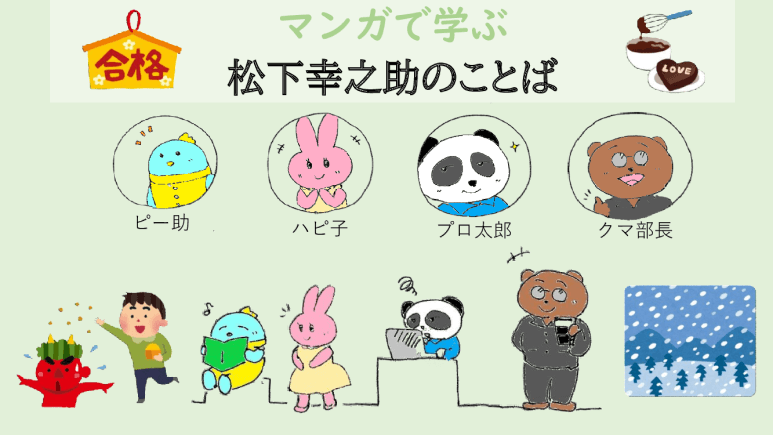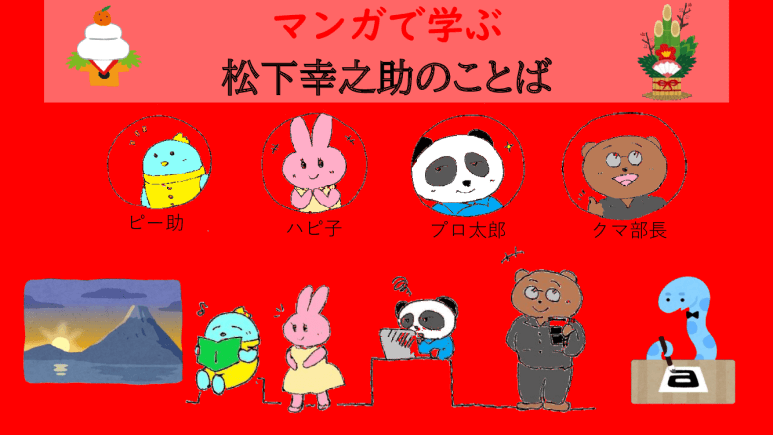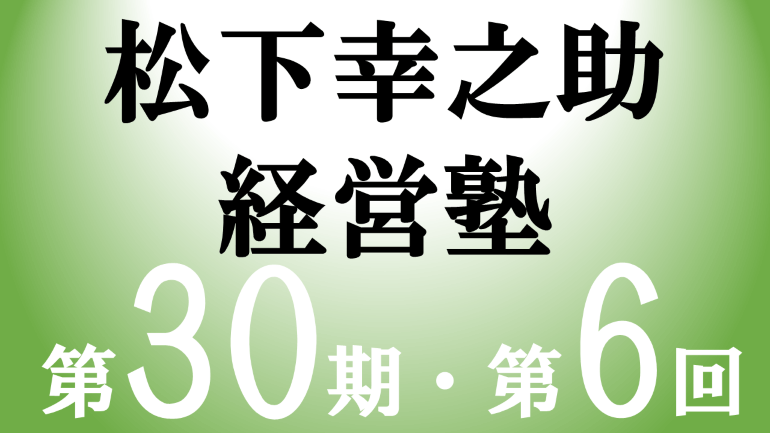「任せて任せず」。 松下幸之助のマネジメントの基本姿勢です。その実践に欠かせない、部下とのコミュニケーション・ツールとして、松下は「電話」を大いに活用しました。
詳細
松下幸之助は自らも述べているように、生来蒲柳の質でした。しかしそのおかげで「身体を大事にしたし、人に頼んで仕事をしてもらうことも覚えた」といいます。自分ができない仕事は人に頼んでやってもらえばいい。社会の繁栄、日本の発展のためにやるべき仕事であるなら、信頼できる適材を適所にあて、任せ、成し遂げてもらえばいい。権限を委譲し、自主責任経営を行なってもらおう――。この考え方が、松下電器を飛躍、成長せしめた要因の一つであり、そのマネジメントの実践において、松下が常に心がけたのが「任せて任せず」でした。基本的には任せる。しかし最終責任者として、仕事の経過を絶えず気にかけ、ときに報告を求めて、問題がある場合には適切な助言や指示をしていく。あまり細かな口出しはせず、脱線しそうなときに注意する、という行き方です。
ただ、「任せて任せず」のマネジメントは、全体の顔が見渡せ、自分の声が届く程度の職場の長であるうちはいいのですが、人員が増え、職種、職場が様々に分岐するようになると、「任せず」を実践する努力や工夫が重要になってきます。
1918年、3人ではじめた町工場を松下は急成長させ、1930年代中頃には2000人を超える大企業に育てあげました。その飛躍ぶりに人材を集めるにも苦労したようで、「店員養成所」を開校し、自前で人を育てるとり組みをはじめたのもこの時期でした。そうして「物をつくる前に人をつくる」態勢を整えていったのですが、実際は「物をつくるなかで人を育てた」といえるでしょう。
現在、パナソニックの本社がある門真市に本店を移した1933年以降、松下は毎日の朝会の場で、従業員に話をするようになります。大勢が同時に同じ話を聞く。その話には会社の方針や理念、トップの哲学が盛りこまれる。それは職場全体の一体感を高めるうえで大いに役立ったにちがいありません。 さらに松下は、離れた職場の部下にも語りかけます。朝礼のあとにとりかかったのは、各工場長への電話による経営指導でした。片手に工場別人員日報、片手に受話器。そして電話の向こうに、矢継ぎ早に質問を飛ばしたといいます。
「きみんとこ、えらい欠勤が多いなあ。理由は?」 「欠勤の理由がわからんて? そんなことで人が使えるか」 「きょうはえろう人を採用したね。どの工程に使うのや」 「人を増やさずに増産するしかけはあらへんのか」 「そのコストはいくらや。そら、高いがな。そんなもの原価計算見んでも常識でわかるがな。きみ、工場長を何年やってるねん」 「きみの言うこと、ようわからんなあ。きみ、ぼくの言うことわかっとるんかいな。ちょっとこの問題ややこしい大事なことや。あしたきみの工場へ行くから、ようわかるように教えてくれへんか。頼みまっせ」
各工場長たちも朝から随分と気が引き締まったことでしょう。さらに次の仕事はというと、各営業所長、つまり営業の第一線への電話による督励でした。
「今度の新型の商品、あれ、どうや。代理店さんはどう言ってはる。小売店はどうや。まあ頼むよ。あれは他メーカーにない商品やから。ぼくは自信をもっているんやが、現地のきみが自信もってくれんことにはなあ」 「この間、〇〇さんが大阪へ来て会ったんや。きみがよう面倒見てくれるいうて喜んではった。きみはどう思うか知らんが、真面目な人やが、ちょっと神経質な人やな。取引してから何年になるのかね。それにしてはもうちょっと売りを伸ばしてもらえるはずなんだが、ちょっと伸びが少ないね。細心な方だが、商売は細心ばかりではいけない。事によっては大胆に行動することも大事やと思うねん。それをどう導くか、励ますかが代理店や松下電器の仕事、つまりきみの仕事のポイントや」「堅すぎてもあかん、柔らかすぎてもあかん。その時々に自在にいきいきと知恵を出すことやな。これ、君わかってくれや。頼んまっせ。これが商売のコツだと思うがどうやろ。それをあんじょう、うまくやれると、代理店も販売店も、それからきみの部下もみんな見習って、一人前に育っていくねん」
お客様、取引先、世間一般の人々の実態を、営業所長がどれだけ把握しているかを試しているようにもみえます。逆に営業所長は、松下から問われ、語りかけられる言葉のなかに、商売のコツ、さらにはお客様大事を掲げる一商人としてのあるべき姿を学びとっていたのでしょう。
松下はこのように電話をマネジメントに巧みに生かしたわけですが、翻っていまは、情報伝達手段がますます進化・多様化し、ツールを使いわけ、使いこなす仕事力がいっそう求められる時代です。けれども結局のところ、伝える方も受ける方も人間であるという点は、どんなに時代が進んでも変わるものではありません。自身の経営哲学をまとめた『実践経営哲学』で、松下は以下のように記しています。
経営は人間が行うものである。経営の衝にあたる経営者自身も人間であるし、従業員も人間、顧客やあらゆる関係先もすべて人間である。つまり、経営というものは、人間が相寄って、人間の幸せのために行う活動だといえる。したがって、その経営を適切に行なっていくためには、人間とはいかなるものか、どういう特質をもっているのかということを正しく把握しなくてはならない。
マネジメントの衝にあたる人は、まず人間の本質を正しく把握することが必要である。そのうえで、部下が自らの特質を最大限発揮して大きな成果を生みだせるよう、適材適所を実践し、できるかぎり声をかけ、絶えず導いていく――。そうした松下も追求した理想のマネジメントの実践に、誰にも負けない熱意をもって日々とり組むところに、情報伝達ツールをうまく活用するための自分なりの創意工夫も、適宜生まれてくるといえるでしょう。
PHP研究所経営理念研究本部