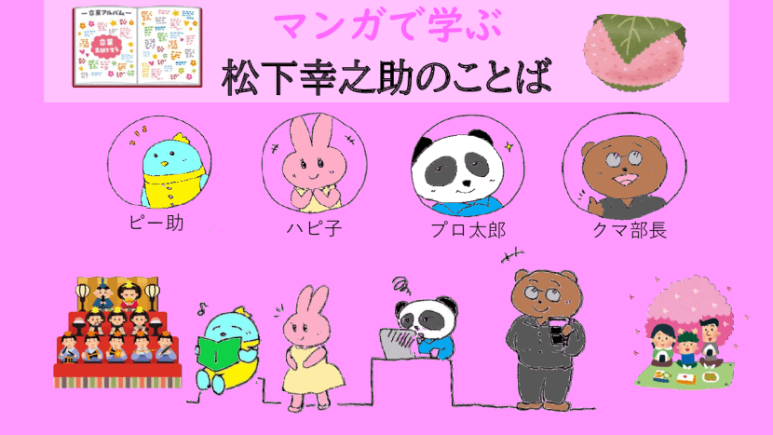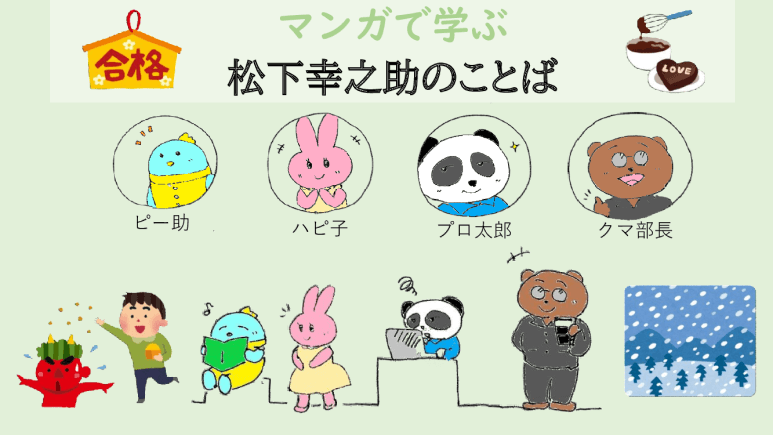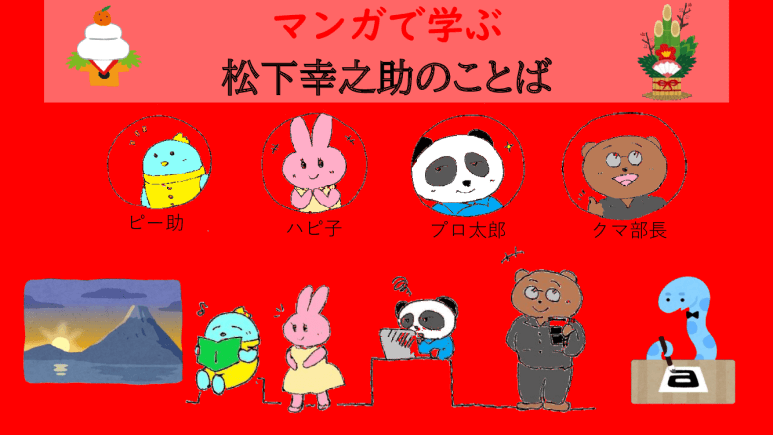経営は人間が行なうものであり、人間が幸せになるために行なう活動である――。 そう信じた経営者・松下幸之助にとって「経営力」とはどのようなものだったのでしょうか。
(2014.9.25更新)
詳細
日本が開放経済体制に移行、貿易自由化に踏み込んだ1960年代、松下は、日本企業が自ら不利な条件を克服し、国際競争に勝ち残るには「何といっても経営力しかない」と述べています。また当時から、国際競争力の強さを如何なく発揮していたトヨタ自動車の経営に敬意を表し、「トヨタ自動車の今日あるのは、石田さん(故・石田退三氏〈当時トヨタ自動車工業会長〉)独特の精神といいますか、トヨタ自動車がもつところの経営力があったからだと思います。そういうものを中心として、技術、販売、一切のものがいまや世界化しつつある、こういうふうに感じます」(1965年の発言)と評してもいます。それほど、松下はこの「経営力」というものを重視していました。以下は戦後の苦境期、1948年7月に当時社長の松下が、松下電器社内で発信された「経営革新社長指令」の中で語ったものです。
経営革新の断行に当ってその基本をなすものは卓越した経営力である。戦時戦後を通じて経営力は著しい低下を来し会社全般の活動力を鈍化させたが、今こそ再び経営力を強化して、これを会社経営理念であるところの、社会的必要な優良品の生産、従業員高水準給与の確保、経営の維持発展の為の適正利潤の確保の諸点に発現させ生産能率の向上、市場競争への必勝態勢の整備・利潤確保による増資態勢の確立を期さなければならない。経営力の発揮は独断から出発した独裁であってはならない。広く合理的に衆智を集め、全員の情熱が結集されてはじめて強力な経営力が形成されるのであって、これが社長をはじめ各首脳者を原動力として会社の細部まで滲透するとき、我社の経営は危機を突破して安定圏に入り、将来の躍進を約束することができるのである。この意味で社長は全従業員の協力を要望し提案を期待する。
(『社長所信集・1』〈1959〉より)
ここで松下がいう経営力とは、会社全体の実力を指しており、経営理念を実践する力、すなわち社会に繁栄をもたらし、従業員を幸せにするための力として認識していることが看取できます。
その後、松下電器はこの最大の困難期を乗り越え、事業を急速に伸展させていきます。オランダのフィリップス社との技術提携(1952年)、5年後に800億円の販売目標を設定した「5カ年計画」の発表(1956年)、販売会社の設立開始、ナショナルショップ制度発足(1957年)、のちに「熱海会談」とよばれる全国販売会社代理店社長懇談会(1964年)後の販売制度改革――。経営力を試される機会が幾度となくありました。
とくにフィリップスとの提携における交渉では、世界最高峰の技術力をもつ大企業に、松下電器の経営力を「経営指導料」として認めさせ、条件改善に成功しています。松下はこのときの体験を、経営の社会的価値を高める一役を担うことができたものと感じていたようです。
のちによく「経営は生きた総合芸術」というようになったのも、経営というものに、芸術と変わらないほどの社会的価値が認められ、経営者自身もその自覚を強くもつところに、事業の発展、ひいては日本経済全体の発展があると考えていたからでした。
一方で「経営は人間が行なうもの」であり「人間が相寄って、人間の幸せのために行なう活動である」という信念をもっていた松下は、経営を担う人間の力、経営力を適切に把握することなしに、会社の発展はありえないことも重々心得ていました。
経営は人間が行なうものである。そして、人間の能力というか、経営力というものは、人それぞれに異なるであろうが、いずれにしても人間は神のように全知全能というわけではないから、その力にはおのずとある一定の限度がある。したがって、事業を行なっていくについても、そうした一定の限度を考えつつ、(中略)その時々における自分の力の範囲で経営を行ない、社会に貢献していく、いいかえれば「適正経営」という考え方がきわめて大切である。(中略)
私は長年の事業の体験の中で、数多くの取引先を見てきた。その中には、最初は経営が非常にうまくいっているのに、業容を拡大していくにつれて成果があがらないというところが出てくる。そういう場合に、思い切ってその商売を二つなら二つに分け、もとの経営者の人はその一つを見て、もう一方は然るべき幹部を選んで全面的に経営を任せるというようにすると、その二つともが順調に発展していくようになることが多い。結局それは、その経営者の経営力の問題である。(中略)
もちろん、会社を二つに分けるというようなことはできにくいという場合も実際にはあるだろう。そういうときには、一つの会社のままで、部門を分けて、それぞれの部門の運営についてはその責任者に大幅に権限を与えて、あたかも独立会社のごとき実態においてやっていくようにするのも一つの方法である。
私の会社の事業部制というものは、そういうところから生まれた制度である。新しい事業分野が次々にできたときに、私自身が何もかも見るということができなくなったから、それぞれの分野について然るべき人を選んで、製造から販売までいっさいの経営を任せたわけである。そのようにすることによって、会社全体としての総合経営力は高まってくるから、そういうかたちにおいて、人を増やし、業容を大きくしてくることができた。そのように、かたちはいろいろあっても、経営力に応じた範囲で独立会社的に運営しつつ、一歩一歩業容を拡大していくことが望ましいと思うが、その場合、こういうことも考えてみる必要がある。それは、そうしたそれぞれの部門の規模ということである。もちろん、それぞれの人によって経営力は異なるし、また人間の力というのはだんだんに成長していくという面もあるから、あまり固定的に考えずに、実情に応じた姿にしていくのが一番いいと思う。
(『実践経営哲学』〈1978年〉より)
松下はもちろん、この「事業部制」のリスクについてもよく認識しており、経営力のある人なくして「事業部をつくったならたいへん」なことになる、事業部は潰れてしまう、と述べています。
結局のところ、その時々の会社の人間の力、経営力に応じて融通無碍に組織形成がなされる姿が望ましいと考え、松下はその実現をめざすとともに、自社と自らの経営力の向上に傾注し続けたのです。
松下幸之助「経営力」語録
・広く合理的に衆知を集め、全員の情熱が結集されてはじめて強力な経営力が形成される
・経営力の乏しいところではいかに立派な人材を得てもその人材が生きてこず、むしろその人々に煩悶を与えることになる
・みんなに好まれるような製品をつくるということも、経営力があればできる
・財務内容をよくするということも、経営力があって立派な経営が遂行できれば、それは生まれてくる
・今かりに、いい製品、いい財務内容があっても、経営力がなかったらそれらはやがて失われてしまう
・会社を見るには、経営力があるかどうか、したがって経営陣がいいか悪いかということがまず問われなければならない
・組織で動くということも、むろん大事でありますが、組織で動くにしましても、組織そのものは決して仕事をいたしません。組織を組み立てたならば、その組織を動かし生かすところの運営力と申しますか、経営力と申しますか、そういうものがあって初めて効果がある
・大きくなればそれにふさわしい組織が必要であるが、同時にそれを動かしていくところの経営力というものが、それに併行して、あるいはそれ以上に発生していかなければ、その組織は生きてこない、いわゆる組織負けになってしまう
・経営力のない人が会社の社長になったら、会社がつぶれてしまう
・会社や商店の経営でも、主人公(社長)自らが経営力をもたなければ、しかるべき番頭さんを求めたらいい
・経営力の大切ささえ忘れなければ、やり方はいくらでもある
PHP研究所経営理念研究本部
関連書籍のご案内