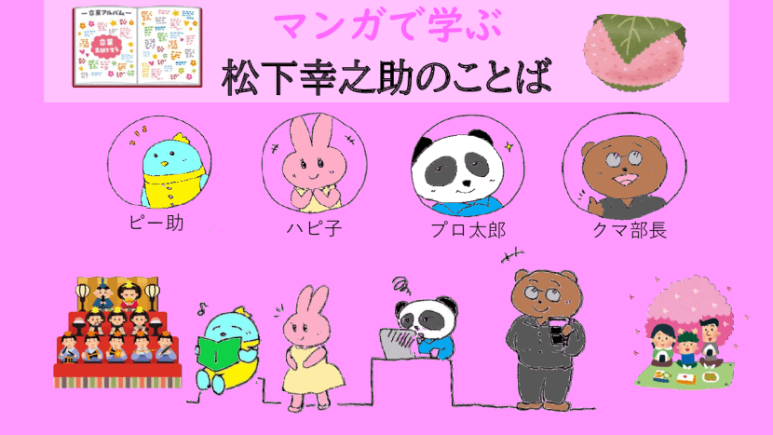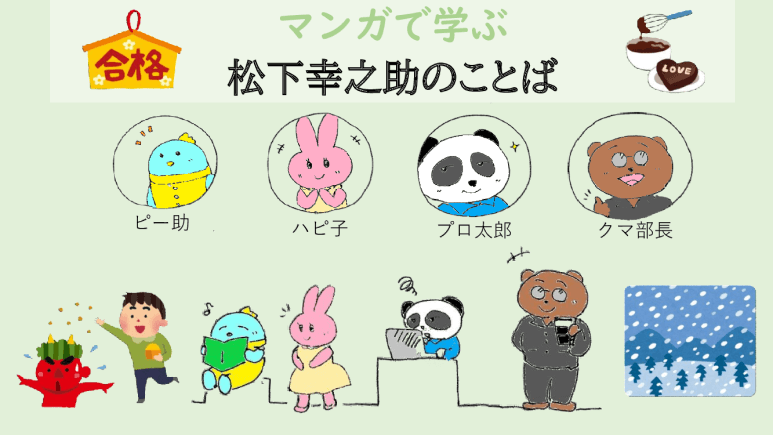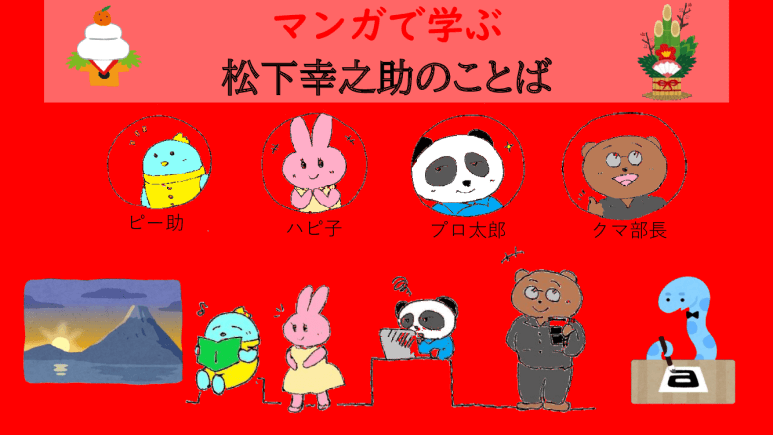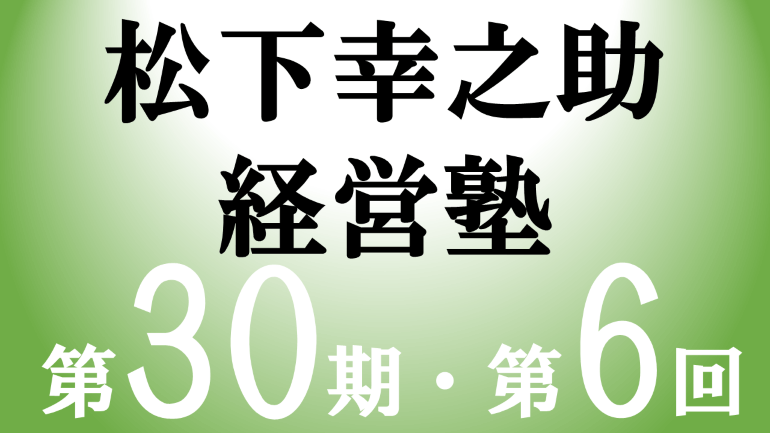日本国民にとって悲しい記憶となったあの「3・11」以後も、各地で地震等による災害が断続的に発生しています。東日本大震災(2011)からの復興・再生とともに、新たな災害への対策が国内政治の喫緊の課題となっています。
松下幸之助が遭遇した最大の人災といえば太平洋戦争でしたが、最大の自然災害は、戦前の関東大震災(1923)であり、室戸台風(1934)でした。
それではこの「震災」というものについて、松下はどう考えていたのでしょうか。
(2013.4.25更新)
詳細
1923年9月1日、関東大震災が発生しました。松下幸之助はその被害を直接受けたわけではありませんが、東京に設けていた出張所に勤務の義弟・井植歳男氏(故人・三洋電機創業者)の所在が一時不明になります。初期の松下電器(現パナソニック)発展に大いに貢献された人物です。運良く災禍を逃れ、4日後に大阪にひょっこり戻ってきた井植氏をみて、ようやく松下も安堵します。
それからの松下電器はというと、震災の復興需要でさらに繁忙をきわめることになります。しかしながら、松下にとってこの日の記憶は忘れ難いものであったらしく、10年後の1933年9日1日の朝会でこう述べています。
「測りがたきは人の世の常とはいえ、あの大異変を一瞬前に知りえたなんぴともなかったことを思うとき、あまりにも人間のはかなさを考えさせられるではないか。さればわれわれは、この日において強くこれを意識し、変に臨んで決して狼狽せず、たとえ前に死が迫るような場合にも従容とし、のちに悔いを残さぬよう常に十分心がけ、何ごとをなすにも最善を尽くしておかねばならぬと、きょう、記念日にあたって深く感じたのである」
『松下幸之助発言集29』
自然災害を現実として受けとめ、それを教訓に日々悔いなきよう、仕事に最善をつくす。松下は、社員に語りかけつつみずからの心に期したことでしょう。 ちなみにこの大災害で、松下は大きな「恩恵」も受けることになりました。それは松下を、後々技術面で支えていく中尾哲二郎氏(故人・松下電器元副社長)との出会いです。震災で焼け出され、大阪に来て、ある工場で働いていた中尾氏の技術と人柄を認めた松下が、松下電器で引き受けたのです。
このことは『縁、この不思議なるもの』という著書に詳しいのですが、松下は後年、「もし、大震災がなかったら」、中尾氏と出会うことがなかっただろうと述懐しています。中尾氏の活躍なしに、初期の松下電器がラジオなどの開発を実現できたかどうか、そのことをいちばん知っていたのは松下自身です。
新商品開発に際し、発意するのは松下でしたが、その意を受け、ことごとく「物」にしていったのが中尾氏でした。松下は自伝のなかで、「爾後今日まで、終始一貫、奮闘努力、熱誠の人として松下電器建設に邁進を続けていてくれることは、周知のとおりである」(『私の行き方 考え方』)との賛辞を中尾氏におくっています。没後にはその遺功をたたえ、「稀有の人」であったと評したほどでした。
「企業は人なり」を信条とした松下でしたが、唯一無二の人材という「恩恵」を与えてくれたのが、皮肉にも関東大震災だったのです。そしてこの不思議な機縁は、松下が後々に確立していくみずからの人生観や商売観・経営観に大きな影響を及ぼしていきます。
「こけたら立ちなはれ」――後日、多くの方々に知られるようになった、この松下の言葉が生まれたのは、1934年9月21日、関西エリアを蹂躙し、3000名もの死者を出した室戸台風のときでした。このとき、前年から大阪の門真に本社を構えることになった松下電器も大損害を被ります。周囲の小学校が倒壊するといった痛ましいニュースが飛び交うなか、松下は、昼近く、ようやく風がおさまりはじめた頃に本社前にたどりつきます。そしてその惨状を見、こう言ったのです。
「こけたら、立たなあかんねん。赤ちゃんでも、こけっぱなしでおらへん。子供でもすぐ立ち上がる。そないしいや」
『叱り叱られの記』(後藤清一著、日本実業出版社)
後藤清一氏は、松下の愛弟子的存在の一人です。氏の自叙伝『叱り叱られの記』には、当時の状況が詳しく記されており、その潔さを現場で見たことで、後藤氏は、経営者としての松下に信頼と尊敬の念をいっそう深めたようです。前年に本社移転が完了したばかりで、希望に湧き立ち、攻めに転じる矢先に甚大な被害を受けたのですから、松下の心情を察するに余りあります。にもかかわらず松下は、落胆しても落胆せず、困難を困難とせず、即座に復興に向けて動き出し、お得意先へのお見舞いも社員に指示したといいます。
しかしその松下も、さすがに太平洋戦争(1941~1945)後は思い悩み、煩悶をくり返します。それでも悩み抜いた挙句に、ついには自力で立ち上がり、物心両面の繁栄を願って、PHP活動を開始します。その研究会のなかで「自然の恵み」をテーマに議論がなされたとき、以下のような質問を受け、自然災害に対する心のもち方についてみずからの思うところを述べています。
「質問者:震災とか大水によって、農作が損害をこうむっております。これは非常に天の恵みに反すると思うのですが」
「松下:それは局部だけ見るとそうですが、そういう災害よりもっと大きな福祉を与えていることを考えなければなりません。たとえば母親は慈愛の心をもっておりますが、場合によっては子を叩きます。叩くということは慈愛の心に反する。母にその心がないかといえば、決してそうではなく、母の愛はやはり一貫したものであります。天災地変はこれを大きくしたものと同じだと思います。個々について見れば、地震に遭った人はやはり痛い。しかし全体の上から見ると、やはり生成発展の姿をとっております」
『松下幸之助発言集37』
この研究会(1948)の頃、福井県でM7・2の激震がありました。そのことにも触れ、福井だけに地震があって、東京などほかの地域に被害がないのはけしからんなどと考えるべきではないし、「これは試練であるといって、もういっぺん立ち上がるところに、前よりもさらに大きな建設が招来されるでしょう」と述べています。こうした考え方に連なって、天災を「天からの励まし」ととらえ、「生も死も生成発展」と考えたのが松下です。その哲学は終生貫かれ、みずからの人生観や社会観、さらには人間観の根底を支えるものとなりました。
「震災後」とどう向きあうか。震災により置かれたそれぞれ境遇は異なることでしょう。ゆえに松下のこうした行き方・考え方が、多くの人々にそのまま通用するかどうかはわかりません。しかし困難にぶつかった際に、こうした松下の言葉にふと耳を傾けてみれば、それぞれの困難を打破する新たな発想や視点を生みだすきっかけにはなることでしょう。
PHP研究所経営理念研究本部