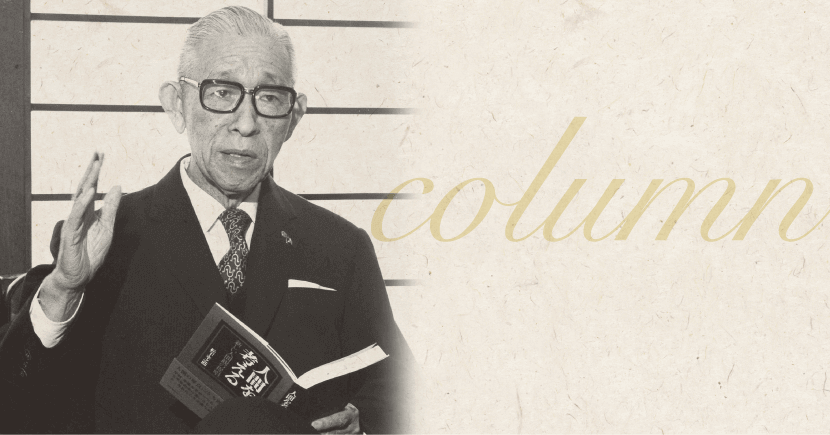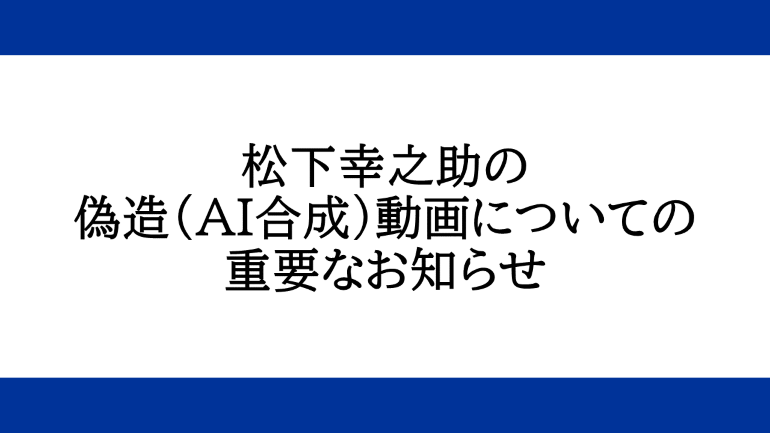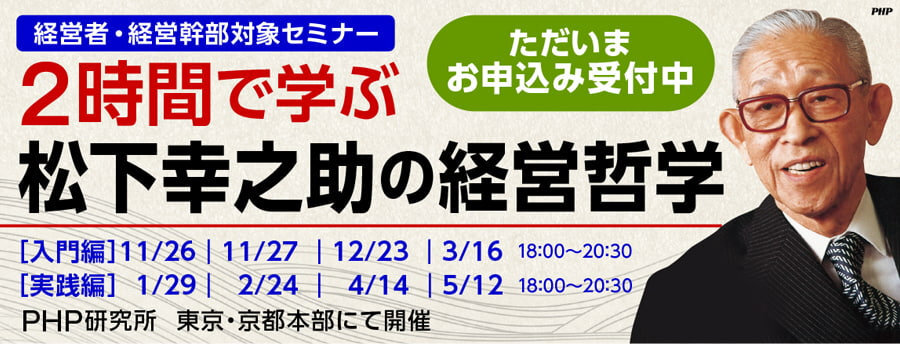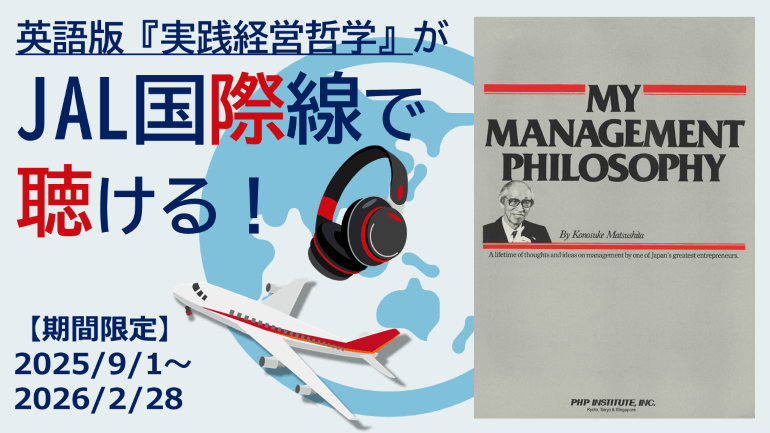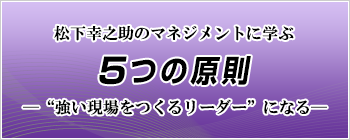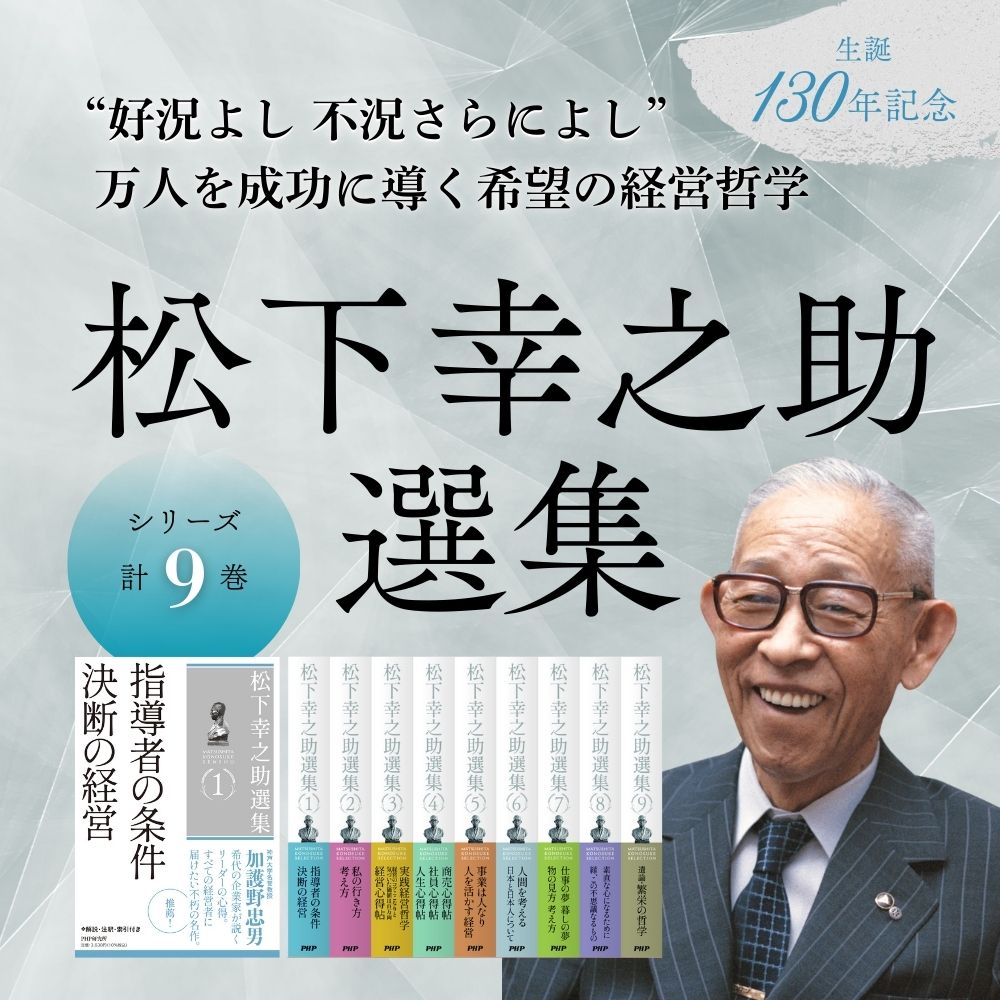昭和57(1982)年5月、松下幸之助を中心に結成された大阪の和歌山県人会「音無会」は創立30周年を迎えました。「音無会」は、熊野本宮大社の横を流れ、熊野川にそそぐ支流である音無川に由来し、「紀伊の国は音無川の水上に~」という古唄にちなんでいます。また政治活動などをせず、おとなしく語り合うという意味も込められました(※1)。会員数を限定する和歌山県人会について、その歴史は明治初期までさかのぼることができます。
和歌山県人会の発端は明治初期、東京の第一高等中学校の学生が中心になって結成した和歌山学生会です。メンバーが社会で要職に就くようになった昭和初期、県人会は再び活発に活動するようになりました。大阪では栗本勇之助氏を中心に「木友(もくゆう)会」、東京では下村宏氏を中心に「紀友(きゆう)会」が結成され、幸之助は昭和12(1937)年に「木友会」に入会しています(※2)。東西の県人会の交流も活発に行われ、昭和15(1940)年4月、大阪と東京で開かれた松下正治・幸子夫妻の結婚披露宴には、和歌山県人会会員が参集しました(※3)。
太平洋戦争で空襲が激しくなると、和歌山県人会はやむなく解散となりました。戦後、幸之助が中心となり、昭和27(1952)年5月29日、大阪市の清交社において第1回音無会が開催されました。第2回は同年7月26日、兵庫県西宮市の幸之助の私邸・光雲荘で開催され、会則や名簿ができました。以後は主に8月を除く偶数月の第一木曜日に開催され、昭和49(1974)年からは8月にも定期開催されています。
音無会は創設30周年を記念して、昭和58(1983)年11月27日に『音無会三十年の歩み』(私家版)を作成し、昭和57(1982)年12月2日開催の第171回まで、すべての会合の情報を掲載しました。昭和60(1985)年8月1日、松下電器本社での開催が、幸之助の出席が確認できる最後の記録です。
幸之助の没後も活動は続けられ、メンバーを変えつつ、現在も音無会は定期的に開催されています。
1)私家版『音無会三十年の歩み』(音無会発行、1983年)30~36頁。
2)松永定一『新北浜盛衰記』(東洋経済新報社、1977年)250頁。
3)「松下家の御目出度 平田伯家より養嗣子を迎ふ」『松下電器社内新聞』第67号、昭和15(1940)年6月15日。