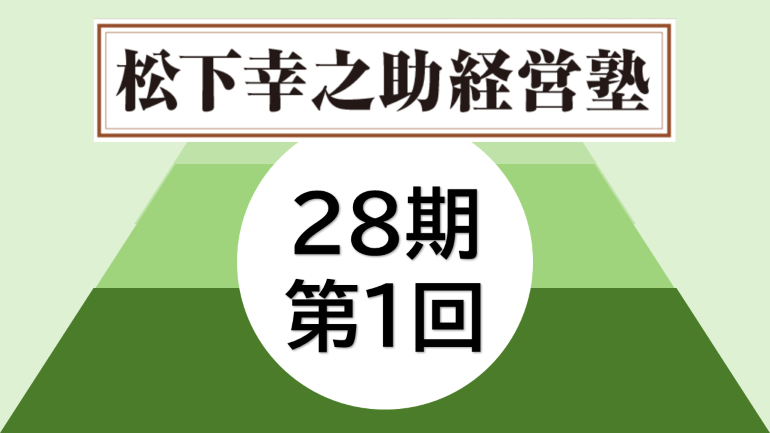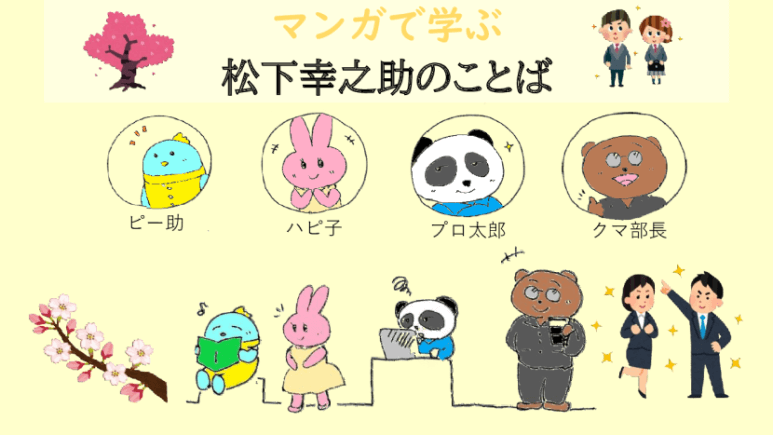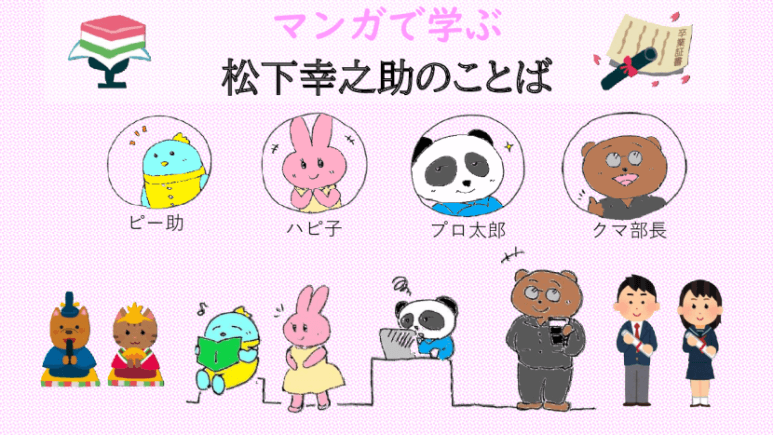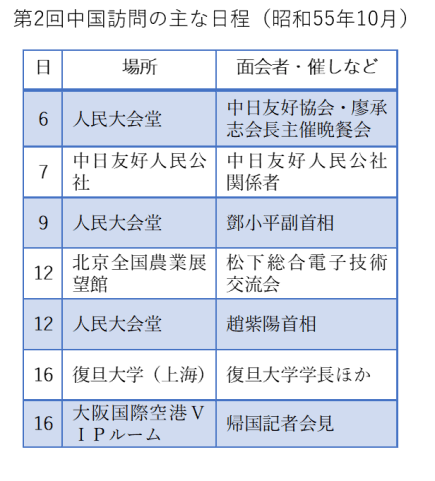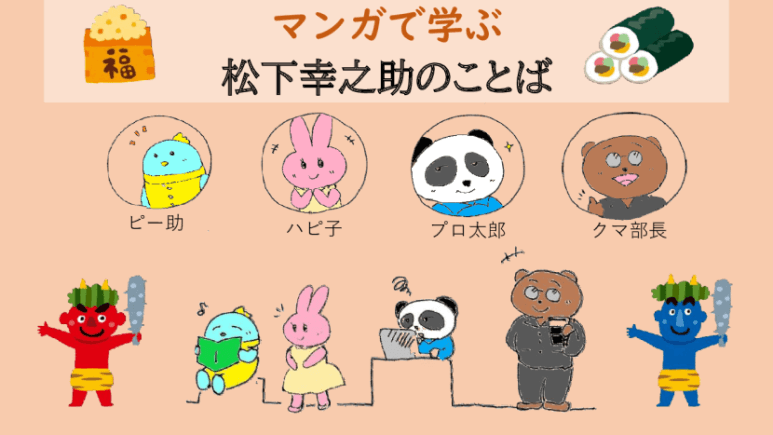明治の先覚者福沢諭吉は、「独立の気力なき者は国を思うこと深切ならず」と喝破している。独立心なき者が何千人、何万人集まったとて、それはしょせんいわゆる烏合の衆にほかならない。国だけではない。会社でも社員に独立心がなければ、同じことである。独立心の涵養こそ、その会社、その団体、その国家の盛衰を左右する重大なカギであることを指導者は知らなくてはならない。
『指導者の条件』(1975)
解説
「烏合の衆」という言葉を、松下幸之助はしばしば使います。指導者が独裁をふるい、組織の構成員の自立心や独立心を奪い、それが道を誤るもととなる。幸之助はそういう過ちを周囲に見聞きし、みずからの戒めとしていたのでしょう。社員に独立心の重要性を説きたかったから、社員稼業という言葉を思いついたのであり、事業部制もそれぞれの責任者に自主独立を求めたがゆえに生まれた経営システムでした。
烏合の衆になるかどうかは、個人の責任に負うところが大きいはずですが、その個人が組織の一員であれば話は違ってきます。幸之助が今回の言葉で示すように、社員が烏合の衆になっているとしたら、それは指導者に責任があるのであり、ましてやみずからの組織がそうなっているかどうかもわからないような指導者なら即刻、その椅子を降りるべきでしょう。
では社員の独立心を高めるために指導者は何をすればいいのか。福沢は『学問のすすめ』という名著でこうも言っています。「独立の気力なき者は必ず人に依頼す、人に依頼する者は、必ず人を恐る、人を恐るる者は必ず人にへつらうものなり」。
何かにつけ、他を頼りにする人ばかりになっていないか。他人(の目、態度)を気にしてびくびくしている人が多くないか。他に媚びへつらう姿をよく見ないか――。そういう雰囲気の有無を指導者は日々自問自答すべきでしょう。その問いに「ない」とはっきり答えることができるようになったとき、その組織には独立心に満ちて行動する人があふれているはずです。そしてそうした社員が集まって、経営がおこなわれていくところに、確かな事業発展が生まれるというのが幸之助の信念でした。
学び
烏合の衆になるな。
烏合の衆にするな。