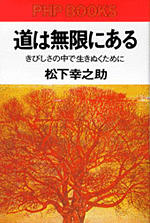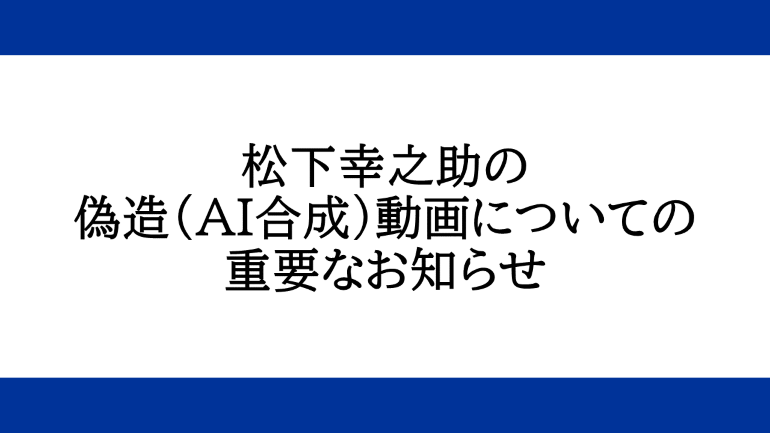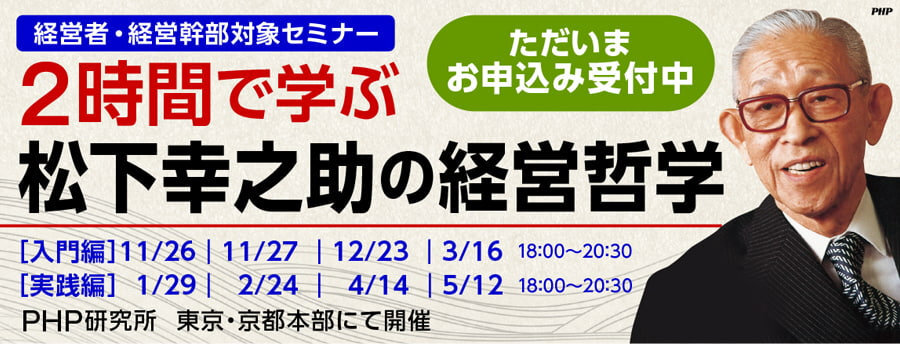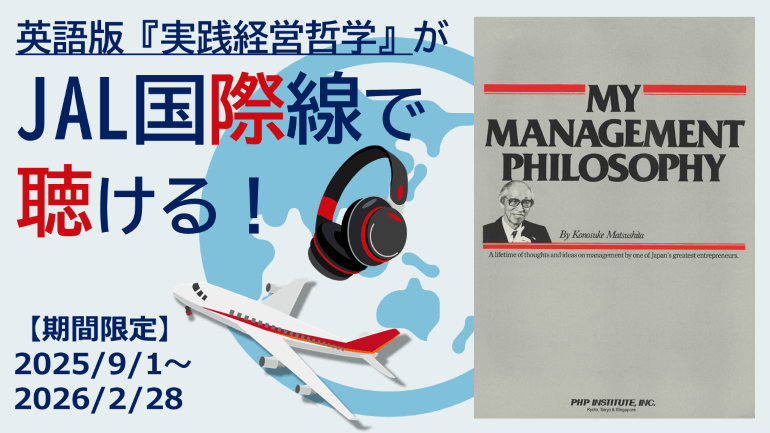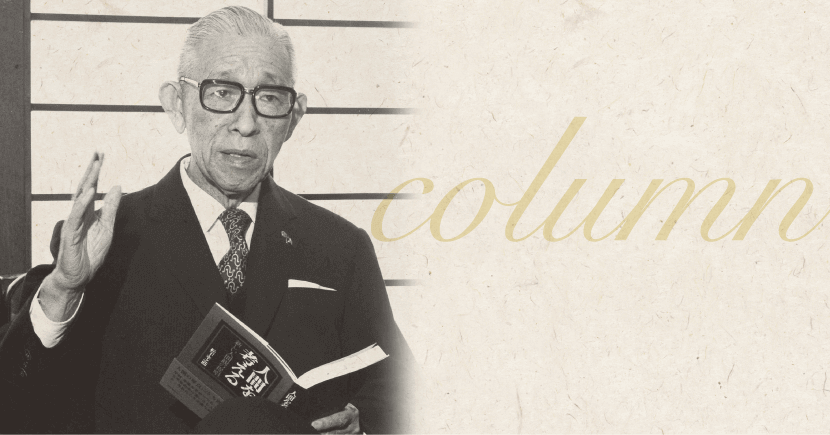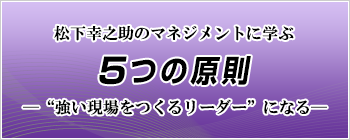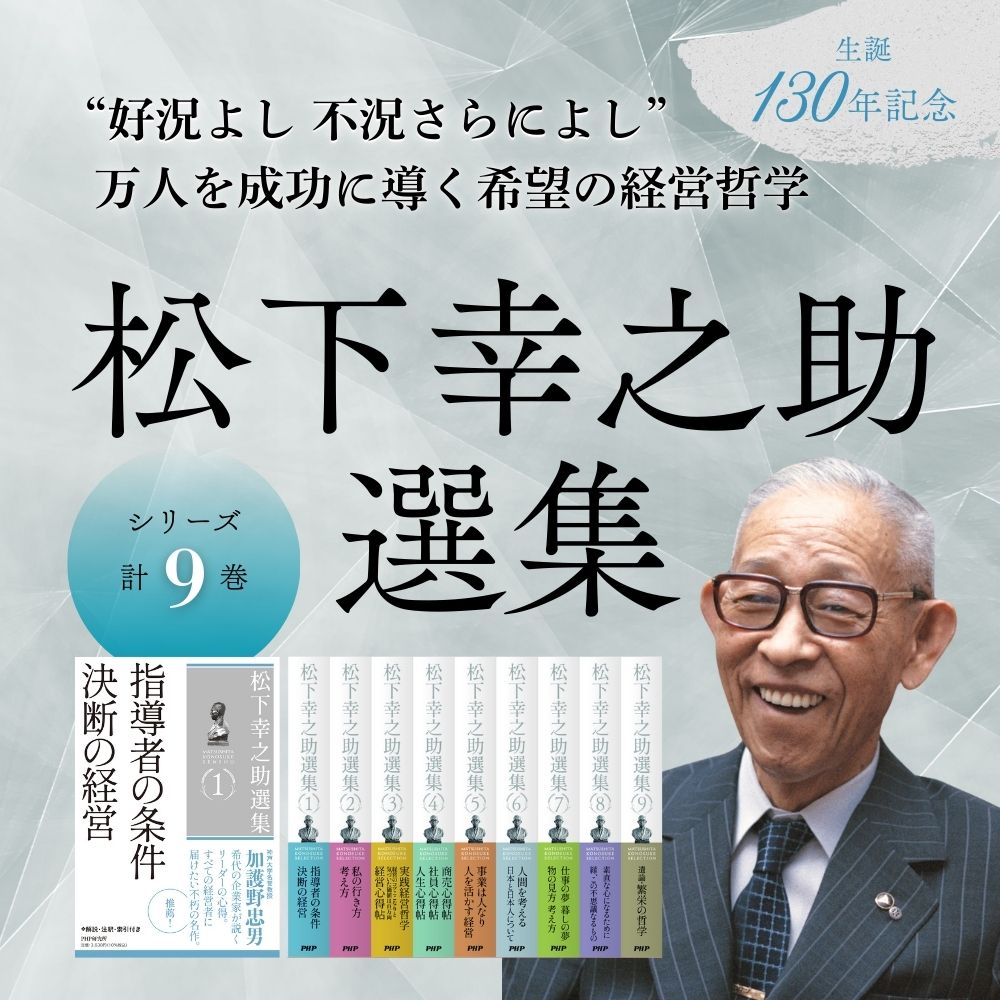困難な時代をいくたびも乗り切った体験をもとに、 厳しさの中で生きぬく心がまえを説く。
まえがき
お互い人間というものは、よい状態がつづいたり、少し事がうまくいったとなると、とかく易きにつきやすいものです。そして、そこに安住してしまって、新しいものを求める熱意が欠けてくるきらいもあるように思います。これも人間の心理として、一面ムリからぬことではあるでしょう。けれども、それでは変化発展してゆく時の流れについてゆけなくなって、やがては進歩向上もとまってしまうのではないでしょうか。
だからやはり、つねにみずから新しいものをよび起こしつつ、なすべきことをなしてゆくという態度を忘れてはならないと思います。お互いが、日々の生活、仕事の上において、そういう心構えを持ちつづけている限り、一年前と今日の姿とはおのずとそこに変化が生まれてくるでしょうし、また一年先、五年先にはさらに新たな生活の姿、仕事の進め方が生まれ、個人にしろ事業にしろ、そこに大きな進歩向上がみられるでしょう。
こう考えれば、まさに"道は無限にある"という感じがします。大切なことは、そういうことを強く感じて、熱意をもってやるかやらないかです。ふしぎなもので、熱意をもって事にあたれば、なすべきことは次から次へと生まれてくるものです。
今日、この社会の動きはまことにめまぐるしく、むつかしい問題も次つぎと起こってきています。が、こうした時期だからこそ、日に新たな心構えで日々の仕事、活動に熱心にとり組んでいけば、次つぎとよりよき知恵も生まれてきやすいのではないでしょうか。
みなさんが、そうした日に新たな考えをもって生活し、活動し、仕事を進めていく上で、私のこれまでの体験が何らかの参考になればと思い、若い人、青年社員などへ私がこれまで話してきたことを、まとめてみたわけです。この本が多少なりともみなさんのご参考になるなら、まことに幸せです。
松下幸之助
目次
| 一 | 困難をのりこえるために | |
| 志を固くして | 11 | |
| 困難に直面しても | 16 | |
| 志を失わなければ | 19 | |
| 困難を打破する道 | 22 | |
| 事があってこそ | 25 | |
| 弘法大師の一念 | 30 | |
| 二 | 覚悟をかためて | |
| 大きな力によって | 35 | |
| 迷いつつ進むけれども | 38 | |
| 会社意識をもつ | 43 | |
| 武士道と産業人 | 48 | |
| どんなに世の中が乱れても | 54 | |
| 大いに心配しよう | 58 | |
| 三 | 実力を伸ばす | |
| 名人になれないまでも | 65 | |
| 自己認識の大切さ | 70 | |
| 訓練を怠らない | 74 | |
| 実力の伸ばし方 | 78 | |
| 一人前になれば | 85 | |
| 成長の度合をはかる | 91 | |
| 四 | よりよき日々を | |
| 変化する心だから | 99 | |
| 用いさせる技術の評価 | 102 | |
| 平凡な仕事を確実に | 109 | |
| 価値ある仕事を | 112 | |
| 末座の人の声を聞く | 116 | |
| 社長を若返らせる | 121 | |
| 五 | 人間を見つめて | |
| 人間としての尊さ | 127 | |
| 豊かな精神生活を | 129 | |
| 尊さを忘れている | 134 | |
| つねに喜びをもって | 137 | |
| なぜPHPを始めたか | 143 | |
| 六 | 日本を考える | |
| 自分を愛し国を愛し | 151 | |
| みずからを知って | 155 | |
| なぜ傍観者がでてきたか | 159 | |
| 伝統の上に新しいものを | 164 | |
| 今後の日本の役割は | 168 | |
| すべての人が自力更生で | 171 | |
| 七 | 正しさを求めつつ | |
| もっと勇気を | 179 | |
| 坂本龍馬の知恵と勇気 | 181 | |
| 意気に燃えて | 185 | |
| 働くことの目的は | 190 | |
| 釆配をふる | 195 | |
| 八 | きびしく生きる | |
| 失敗をしない方法 | 203 | |
| 命をかけて | 208 | |
| 趣味と本業は | 212 | |
| 日々方針をたてて | 218 | |