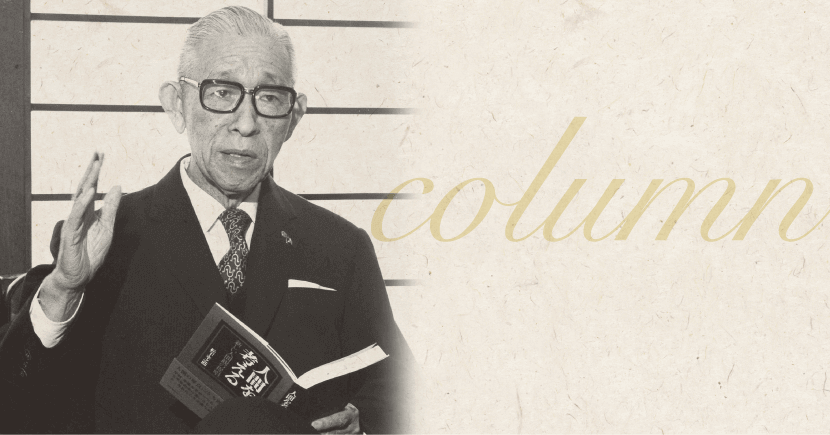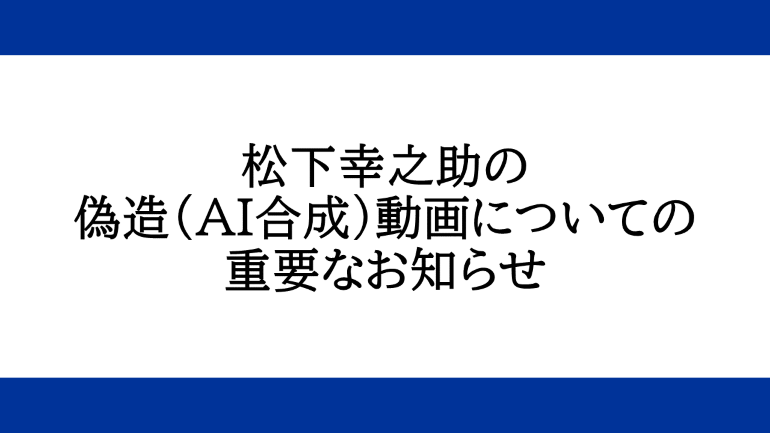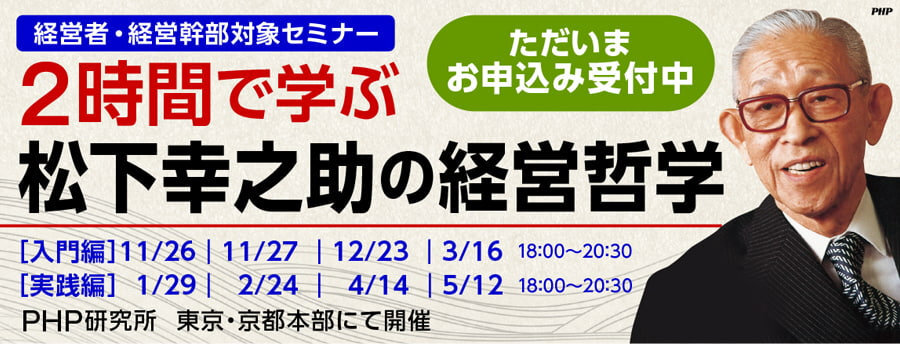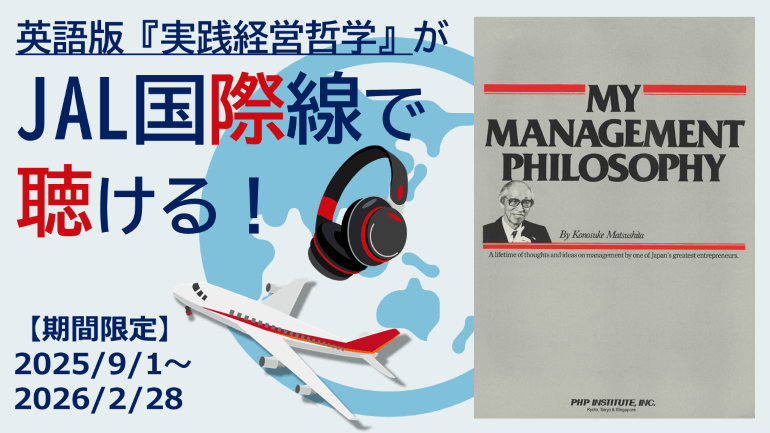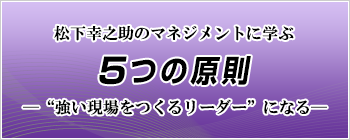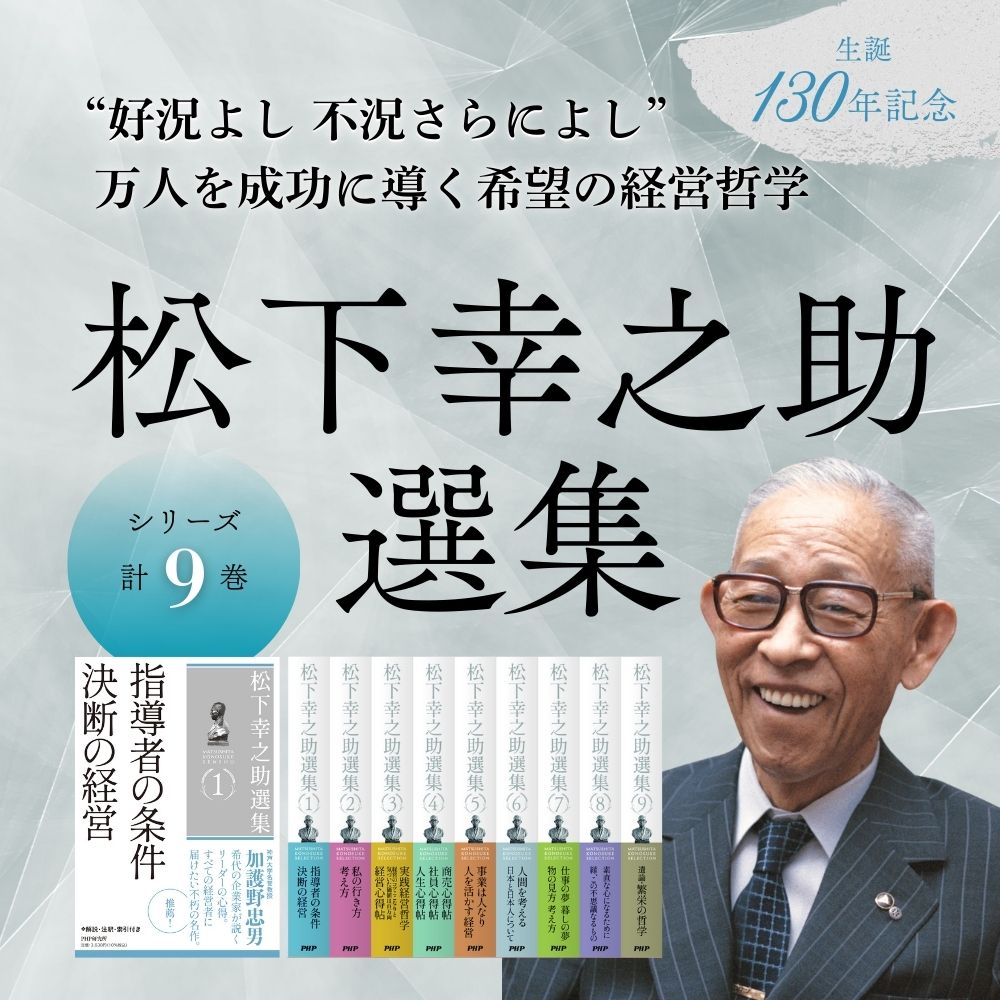日本でもノーベル賞に匹敵する科学賞を創設すべく、昭和58(1983)年10月28日、財団法人国際科学技術財団によって日本国際賞が創設されました。松下幸之助は同財団の会長を務めています。
財団の創設は、さかのぼる昭和56(1981)年、当時総理府総務長官で参議院議員であった中山太郎氏が幸之助に資金の相談をしたことがきっかけでした(※1)。中山氏は大阪選出の議員なので以前から面識があり、幸之助が資金の拠出を承諾したことで、賞を創設する計画が始まっています。
財団の設立を準備する「日本国際賞準備財団」がまず昭和57(1982)年11月に設立され、幸之助が会長に就任しています(※2)。同年12月22日、幸之助はこの賞について松下労組の幹部から質問を受ける機会がありました(速記録№1956)。「いっさいの世話は政府がする」との条件で、資金は幸之助の私財と松下電器で負担することになったと言っています。この時点で賞の名前は「松下賞」ではなく「日本賞」にすることになったと説明しました。
財団法人国際科学技術財団は、昭和58(1983)年5月5日に設立されました。松下電器が創業65周年記念として、同社の株式1,000万株を拠出しています。前日5月4日の終値1,530円で計算すると時価総額153億円。さらに幸之助が総計50億円を順次寄付し、総額203億円の寄付でした(※3)。
第1回授賞式は東京の国立劇場で、昭和60(1985)年4月20日、皇太子夫妻(現上皇夫妻)や中曽根康弘・総理大臣(当時)を招いて催されました。第1回の受賞者は、情報通信分野で、画期的な業績をあげた米スタンフォード大学客員名誉教授のジョン・R・ピアース氏と、バイオテクノロジー研究の先駆者で酵素工学の研究をしたイスラエル・テルアビブ大学教授、エフライム・カチャルスキー・カツィール氏の2人が選ばれています。幸之助は自ら登壇して2人に賞を授与しており(写真)、授賞式の後に行われた祝宴には、幸之助に代わって山下俊彦・松下電器社長(当時)が出席しました(※4)。
1)井塚裕修「松下幸之助創業者様と日本国際賞」『松苑』第5号、松下電器客員会、1992年。
2)「『日本版ノーベル賞』新設」『サンケイ新聞』昭和57(1982)年12月15日付。
3)「文化・学術に温かい手 幸之助さん」『日本経済新聞』平成元(1989)年4月28日付。
4)「第1回日本国際賞」『松下電器社内時報』第949号、昭和60(1985)年5月1日付。