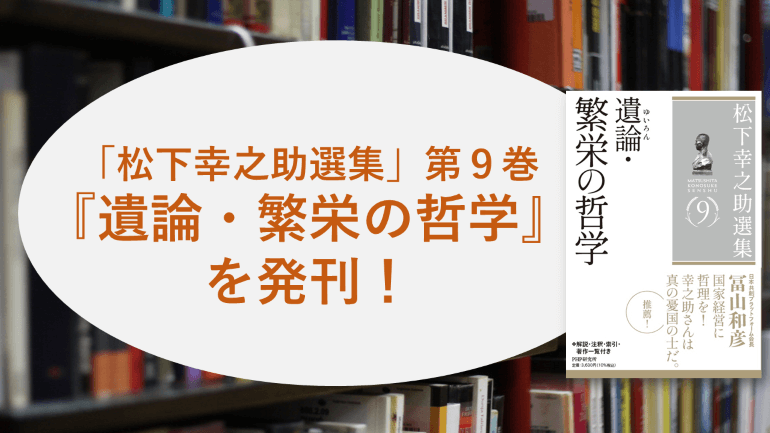昭和十年から数年にわたって、幸之助は、今でいう社内誌にあたる『歩一会会誌』という小冊子に、みずからの生いたち、事業の変遷などを書きつづっていた。大阪の門真から、そのころ幸之助の自宅があった京都の今出川まで、毎月その原稿を取りに行くのが入社してまのないある青年社員の仕事であった。
そのころ松下電器は、すでに従業員三千名ほどの企業に成長していたが、その大企業の社長である幸之助に、青年社員はある種の親近感を抱いていた。
というのは、原稿を取りに行ったときに幸之助が、会社へ行く車にいっしょに乗るよう気やすく勧めてくれたことがしばしばあったし、また、その車中でも、青年社員の両親のこと、兄弟のことなど、いろいろと話を聞いてくれたりしていたからである。
なかでも特に、青年社員が感激したのは、やはり京都から大阪への車中で、幸之助がこんなことを言ったときであった。
「きみも知ってのとおり、最近は松下電器もしだいに業容が大きくなってきて、わしもいろいろな会合に出席を求められることが多くなってきた。ところがわしは、小学校もまともに出ていない状態や。それぞれの会合で話を聞いていると、ときどき話の途中に出てくる外国語がわからんことがあるんや。
そこできみに頼みたいんやが、いっぺん最近日本語化された外国語を拾い出して、それがどういう意味か書いて、わしに持ってきてくれんか」
そう頼む幸之助に青年社員は、“ふつう社長ともあろう人がこんなことはなかなか言えるものではない。それをこの人は、こんなに率直に若い自分に言うなんて、なんてすばらしい人なんだ”と感じ、どんなことがあってもこの会社から離れないでいようという気持ちになったという。