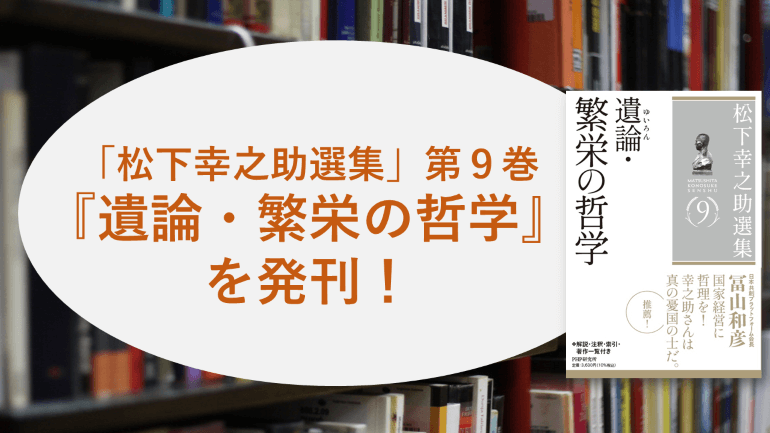昭和六年春、大阪天王寺公園のグラウンドを借り切って、松下電器の歩一会(※)は第一回運動会を挙行した。前夜十時ごろのことである。テントの布設など会場の準備を万端整えてひと息ついた実行責任者は、何気なく夜空を見上げたとたん思わず声をあげた。
「おいッ! 国旗があがってるで」
高さ十七、八メートル、トビ職に頼んで立てた、にわか国旗掲揚台のてっぺんに日の丸がはためいている。開会式のスケジュールは、グラウンドに全員集合してまず国旗掲揚と君が代斉唱、そのあと幸之助の挨拶となっていたはずである。
「どないしょう、きっとトビの親方が、面倒やから初めから旗付けてしまったんや」
降ろそうにも滑車がなく、ただ見上げるばかり。
「しゃあないわ、大将に報告だけしとこか」
幸之助の自宅に電話を入れた。
「遅くまでご苦労やな」
「はあ……」
「何かあったんか、今時分に」
「実は、開会式の式次第を若干変更したいと思うんですが……」
理由を聞いて幸之助の声色がガラッと変わった。
「何やて、そら、きみ、あかんよ。国旗を掲揚し君が代を斉唱してといういちばん大切なところを、最初から国旗をあげとくというんでは話にならんがな。仕事も遊びもいっしょや。しっかり計画どおりにやることが大切なんや。わしも楽しみにしていた運動会やが、もしそんなことならやめてしまったらええ」
責任者は仲間二人とすぐトビの親方のところへ走った。
「こんな夜更けにすんまへん。なんとかあの国旗、あげおろしができるようにしてください」
なかなか承知してくれない。酒を呑みつつ、三人をにらんでいる。三度、四度、その視線に負けずに頼み込む。
「よっしゃ、わかった」
親方のひと声でトビ職が公園に走った。掲揚台を掘り返し、滑車を取り付けたときには、午前零時をまわっていた。
「もしもし」
「わしやけど」
「やりましたが……」
「そうか、そらよかったな。はよ寝えや」
三人はそのときは何か肩すかしをくらった感じであった。
翌日は五月晴れ。国旗がスルスルとあがり、君が代が斉唱され、そして幸之助の挨拶、みな計画どおりに進行した。運動会の後片づけもすっかりすんで宴会のときである。幸之助が、わざわざ三人のところへ来て声をかけた。
「国旗掲揚ではえらい苦労したらしいな。甲斐あってよかったなあ。おかげでええ運動会になった」
三人は疲れがいっぺんに消えていくのを体の中で感じていた。
※“社員全員が歩みを一つに”をめざして大正九年に結成された一種の親睦団体。結成当初の会員は、松下幸之助を含む全従業員二十八名であった。