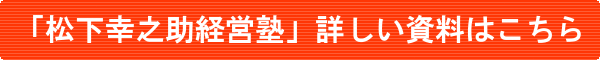4人に1人が65歳以上という「超高齢社会」日本で今、注目されているのが在宅医療である。住み慣れた自宅で落ち着いて療養する。家族に見守られながら安らかな気持ちで最期の時を迎える。そんな安心社会の創造に貢献したいと、在宅医療専門クリニックを開業した伊谷野克佳さん(「松下幸之助経営塾」卒塾生)。その志をスタッフの高度な専門能力と融合させ、組織の力として発揮するためには何が必要だったのか。東京・蒲田のクリニックを訪ね、話をうかがった。
<実践! 幸之助哲学>
チームの力を高めて真に安心できる訪問診療を――前編
「病院で死ぬ」が当たり前の超高齢社会
日本の総人口は、二〇〇八(平成二十)年にピークを迎え、その後二〇一一(平成二十三)年以降は減少を続けている。一方、六十五歳以上の高齢者人口は一貫して増え続け、二〇一七(平成二十九)年には三五〇〇万人を突破。総人口に占める高齢者の割合は二七・七パーセントと、過去最高を更新している。
世界でも類を見ない速さで進行する日本の超高齢化に対して、医療・介護の分野では対策が急務となっている。
その一つが「在宅医療の推進」である。
高齢になると身体の機能が低下し、通院が困難になるケースが増えてくる。そうすると、身体の状態・調子としては本来入院するほどではない患者も、通院困難というだけで入院という選択をせざるをえない状況が生まれる。「本当は住み慣れた自宅で療養したい」という患者本人の希望も叶えられなくなる。
病院は基本的に治療の場としてつくられているので、生活するという観点では必ずしも快適とはいえない。したがって、入院が長引くと「自宅に帰りたい」と訴える人が増えるのである。「せめて死ぬ時は家で」という望みもむなしく、そのまま病院で最期を迎えるケースも少なくない。
一九五〇年代前半では、人が死を迎える場所は「自宅」が最も多く、約八割を占めていた。病院で亡くなったのは一割程度である。現在、その比率は全く逆転し、約八割が病院で、自宅は一割強である。
われわれは、いつのまにか「病院で死ぬこと」を当たり前の常識として受け止めるようになった。もし在宅医療がもっと充実し、誰でもそれを受けられるようになれば、本来入院する必要のない患者は家で療養することができ、家族や地域社会との交流を続けながら、安心と快適の中で日常生活を送ることが可能になる。また、愛する家族に見守られながら、心安らかに死を迎えられる人も増えるはずだ。
在宅医療の充実は、高騰する国民医療費を抑制する方策の一つであるとともに、高齢者の生活の質の向上に資することにもなるのである。
そうした時代背景もあって、近年、在宅患者に対する訪問診療の件数は年々増加している。
では、件数の増加に伴って訪問診療を行なう医療機関が同じだけ増加しているのかといえば、一概にそうともいえないようだ。今回取材をしたのは、そうした数少ない在宅医療のスペシャリストで、東京都大田区および品川区で訪問診療に特化したクリニックを経営する伊谷野克佳さんである。
伊谷野さんは二〇〇五(平成十七)年に独立・開業した。医師になった当初は大学病院や地域の基幹病院に勤務し、心臓血管外科医として活躍していたが、八年目を迎えたところで、在宅訪問医療の世界に舵を切る。そこにはどんな思いがあったのか。
訪問診療を支える「チームの力」
伊谷野さんのクリニックは、訪問診療専門なので外来患者の受け付けはしていない。京急蒲田駅から徒歩数分程度、環状八号線にほど近いビルに、一般企業と同様に入居していた。外来がないので大きな看板もない。
クリニックといえば受付があり、診察や精算を待つためのソファがあって......という光景を筆者はイメージしていたのだが、そこは普通の会社の事務所とそれほど変わらないように見えた。
取材で訪ねた「ファミリークリニック蒲田」では、様々な医療専門スタッフと、それを支える助手や事務スタッフがチームとなって仕事をしている。毎朝、朝礼で全体的な連絡事項を確認したあと、カンファレンス(医療専門スタッフによるミーティング)で個々の患者の容態や診療状況の把握、今後の治療方針や投薬の検討など、情報の共有がなされている。


毎朝9時、スタッフ全員が集合して朝礼が行なわれる
連絡事項の共有のほか、突然指名された人が「最近嬉しかったこと」を話す「ハッピートーク」も特徴の一つ
日常のいいところに目を向けて前向きに生きられるように、という伊谷野さんのアイデアだ
伊谷野さんが重視するのは「チームの力」である。患者が抱える病気の種類は様々であるし、複数の疾病を抱えている人もいる。したがって、一人ひとりの患者に対応するためには、様々な専門医やスタッフがお互いの知識や経験を活かし合い、最善の治療法を見出していくというプロセスが必要になるのだ。
ファミリークリニック蒲田では、総合診療科の常勤医を中心に、皮膚科、整形外科、精神科等を専門とする非常勤医がグループ診療を行なっている。加えて、看護師、理学療法士、さらには地域の介護支援専門員(ケアマネージャー)との連携や相談業務を行なう相談員など、多彩な医療スタッフをそろえ、多様なニーズに応えている。
また、近隣の大学病院、総合病院や専門医療機関との連携態勢も確立しており、専門治療や特殊な検査が必要な場合は、これらの医療機関で受診ができるようになっている。もちろん、必要があれば入院の手配も行なう。
こうした取り組みにより、開業初年度は七〇名程度だった患者数は年々増加し、現在定期的な訪問診療を実施している患者は五〇〇名を超えるまでになった。開業以来、赤字の年度はなく、毎年利益を出し続けてきた。
数字だけを見ると右肩上がりの順調な成長に思えるが、実は数字には表れない危機が何度もあったという。
「多くの人の役に立つ」が最初の志
伊谷野さんの生まれは群馬県桐生市。実家は祖父の代から街の電器店を営んでいた。ナショナル・ショップ(松下電器=現パナソニック系列)ではなかったが、なぜか子供の頃から幾度となく松下幸之助の偉大さを父や祖父から聞かされていた。もちろん、後年「松下幸之助経営塾」に入塾し、その哲学や生き方に密接に触れることになろうとは、この時点では想像すらしていなかった。
中高生の頃から、人間の「生老病死」に深い関心を寄せるようになる。仏教では生老病死は、人間の思い通りにならず、人が避けることのできない四つの苦しみであると教えている。
伊谷野さんは考えた。確かにこの四つは人間の力では避けられない。しかし、「生まれること」はともかく、「老いること」「病むこと」「死ぬこと」に関しては、ただ手をこまぬいているだけではなくて、何か手立てがあるのではないか。つまり、避けようのない現象ではあるけれども、人の手によって緩和したり、予防したりということができるのではないか――と。
こうして伊谷野さんは医学の道を志すのである。医師を目指す伊谷野さんを、父は心から応援してくれた。「自分はお客様にいつも『ありがとうございました』と言ってきたが、医療は逆に患者さんから『ありがとうございました』と感謝される仕事だ」と言われたそうだ。伊谷野さんは、父の気持ちに応えるためにも、世の中の役に立つ医療、人の不安を解消し人に喜ばれる医療を実践しなければならないという思いを強くしたのだった。
大学卒業後は外科医になり、心臓血管外科で仕事をこなす。
「かなりハードな職場でしたが、仕事を重ねれば重ねるほど技術が上がります。自分の成長を実感することができ、毎日が充実していました」
と伊谷野さんは当時を振り返る。
しかし、専門を追究していくと、次第に扱う領域が狭く絞り込まれていく。技術を磨けば磨くほど、専門性が深掘りされていくことになる。該当する病気の患者のためには力を発揮することができるが、自分の専門以外の病気にはかかわれなくなっていく。「多くの人の役に立ちたいと思って医療の世界に入ったのに......」というジレンマを抱えるようになった。
このままスペシャリストの道を究めていくのか、それとも一般的な診療もこなすジェネラリストへと方向転換するのか――悩み抜いた末、伊谷野さんは後者を選択する。
一般的に医師の世界では、学会でどれだけ優れた業績を残せるかが大きな評価尺度となっている。外科なら難しい手術をどれだけ行なったか、そしてそれをどれだけ論文にまとめて発表したかがものをいうわけである。伊谷野さんのように、そこから一般総合診療医になろうとする人は少数派で、主流から外れていくようなイメージを持たれる時代だった。
ただ、伊谷野さん自身は、自分の決断に迷いはなかった。医師を志した時の「初心」を思い起こせば、一般総合診療こそ自分の進むべき道だと思えたからである。
こうして三十代の半ばで独立・開業に至るわけだが、伊谷野さんが選んだのは外来クリニックではなく、訪問診療クリニックだった。
◆理念の明文化と共有で「断らない医療」を実現(後編) へつづく
松下幸之助経営塾
◆講師は?