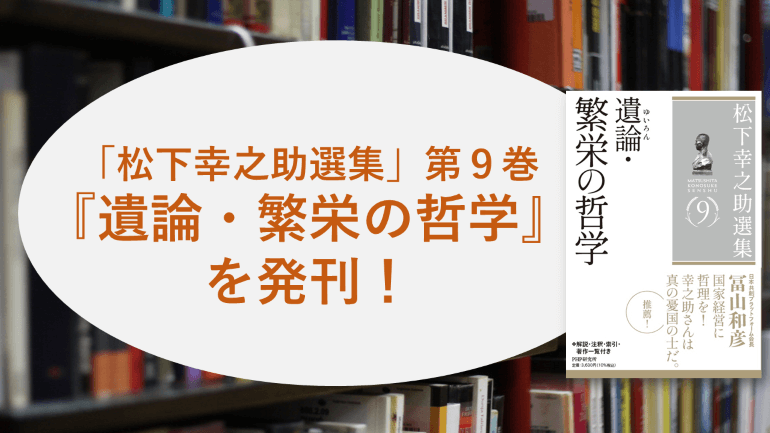昭和三十一年ごろのこと、研究所の課長が手狭になった施設を拡充する決裁をもらうべく、幸之助を訪ねた。幸之助は自室で別の社員の報告を聞いていた。隣の秘書室で課長が待機するうち、幸之助の声がだんだん大きくなってきた。激しい剣幕で怒っている。
“これはえらいときに来たな。こんなに怒っておられるときにこんな決裁を持っていったら、成るものも成らんのとちがうかな。きょうは帰ったほうがいいかな”
迷っているうちに、さきの社員の報告がすんで、課長は入れ違いに、おそるおそる部屋に入った。厳しい叱責の三十秒か一分あとである。しかし、幸之助の表情はすっかりふだんのものであった。
「このごろ研究はうまいこといっているかね」
近況を報告し、決裁を求めると、幸之助は、「よし、わかった」とうなずいて、受話器を取り、担当者に電話をかけて、「いま建物の決裁をしたからすぐ手配に入ってくれ」ということになった。
“わずか一分足らずのあいだに、よくもああパッと切り替えられるものだ、まさに名優や”
そう感じたことを、課長は二十年後に語っている。