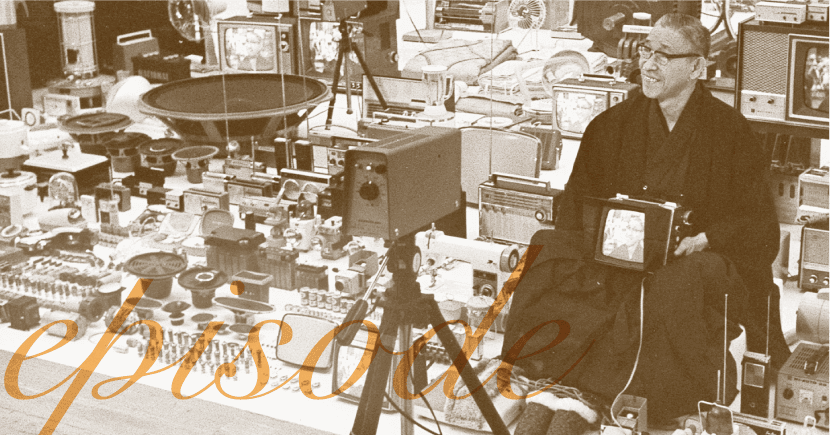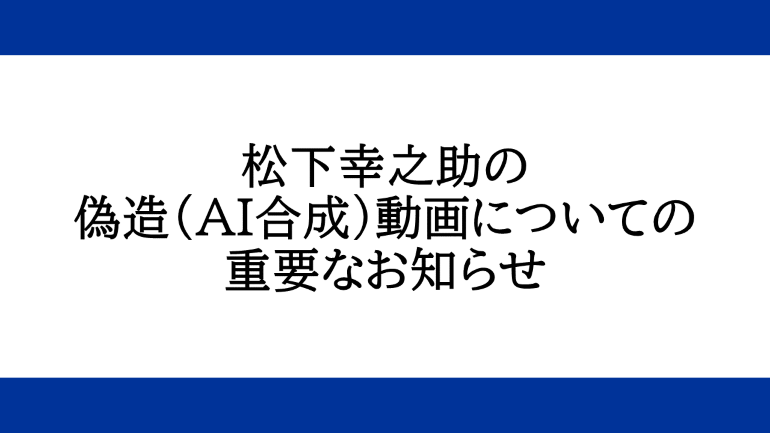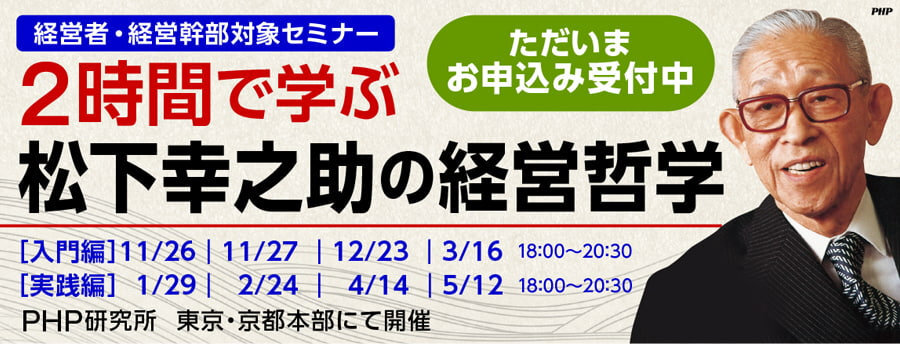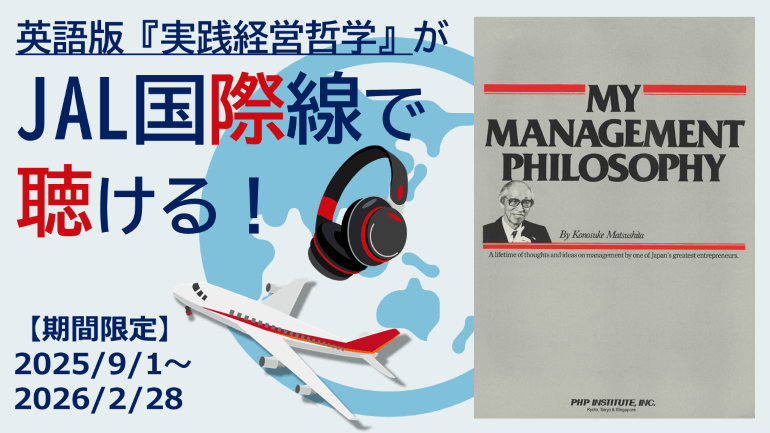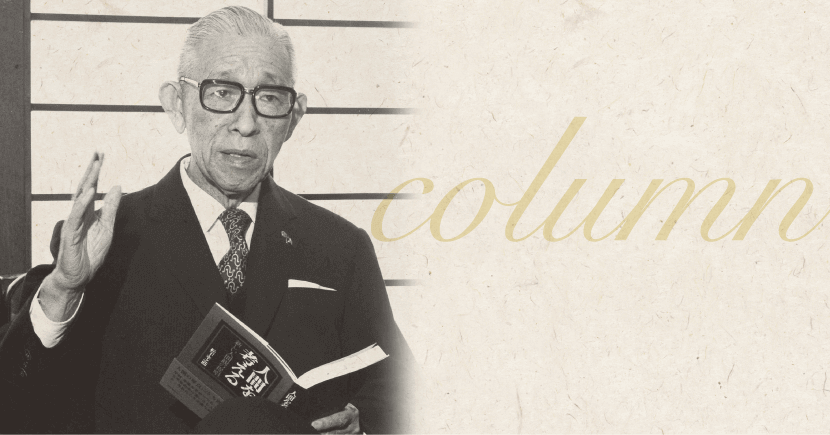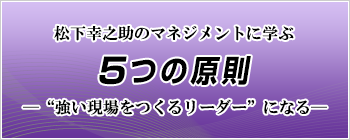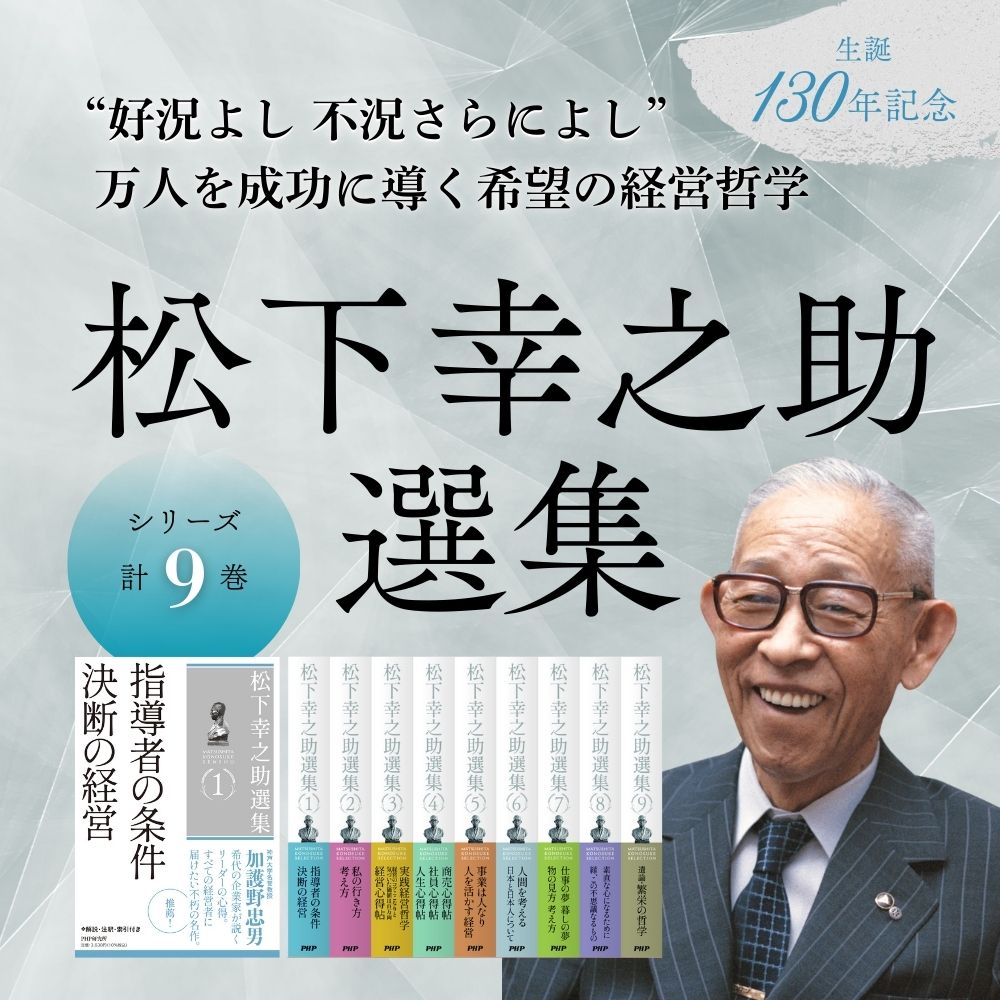ウルトラCのトースター――人を見る眼〈11〉
バイメタル方式の自動トースターが開発されたときのことである。開発にあたった技術者二人が、試作品を持って本社の製品審査室に赴いた。審査室は新製品を検査する部署であるが、二人が廊
思いがけない餞別――情を添える〈11〉
昭和二十四年、戦後の混乱のなかで、松下電器はそれまでの歴史にもその後の歴史にもない、解雇や依願退職を募るという異例の対策を講じつつあった。そうしたなかで、戦前からデザイナーと
いくらで売ったらいいでしょう――共存共栄への願い〈11〉
幸之助が初めてソケットを考案製造したときのことである。ソケットをつくりはしたが、いわばまったくの素人、それをいくらで売っていいかがわからない。 そこで幸之助は、さっそく、
自分の金やったらかなわんけれど......――繁栄への発想〈11〉
幸之助が独立してまだまもないころ、税金は、大きな事業をやっているところは税務署のほうから調査に来るが、小さなところは申告者を信用して、その申告した金額に応じて納めるというよう
不要な書類を一気に廃止――仕事を見る眼〈11〉
昭和三十九年七月、熱海で行なわれた販売会社・代理店社長懇談会(通称熱海会談)のあと、幸之助は会長でありながら、営業本部長代行として第一線に復帰し、経営の改革にあたっていたが、
自分の頭をなでてやりたい――人生断章〈11〉
昭和四十八年七月、幸之助は会長を退任し、相談役に就任した。そのときの記者会見で、「今の感慨は?」と問われ、つぎのように答えた。 「まあ非常によかったという
社員の顔を覚える――情を添える〈10〉
京都東山山麓の真々庵でまだPHP活動を行なっていたころのことである。 幸之助の留守中、たまたま真々庵見学の機会を得た松下電器の社員が、ある部屋の一隅に小さな屏風が立てかけ
人情に厚く人情に流されない――共存共栄への願い〈10〉
昭和二年に新設した電熱部は、幸之助が同じ大開町に住む友人である米屋の主人と共同出資のかたちで始めたものである。当初その経営は友人が受け持った。 しかし、電熱部はスーパーア
女性も入れよう――繁栄への発想〈10〉
幸之助が私財七十億円を投じて神奈川県茅ヶ崎に「松下政経塾」をつくったのは、昭和五十四年六月のことであった。 設立を前に、ある新聞社の女性記者がインタビューをして、「女性は
経営理念を売ってほしい――経営の姿勢〈10〉
昭和四十四年六月、幸之助は、ヨーロッパ視察の途中、西ドイツのハンブルク市に立ち寄った。そして、ハンブルク松下電器を訪ね、そこで日本から出向している駐在員との懇談会をもった。そ