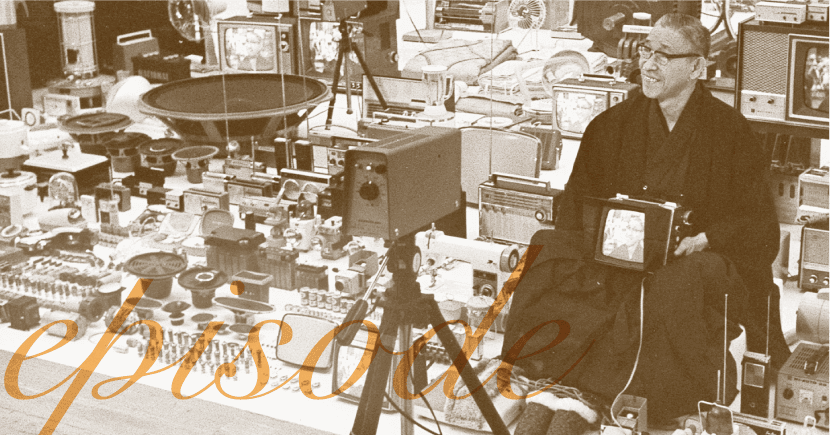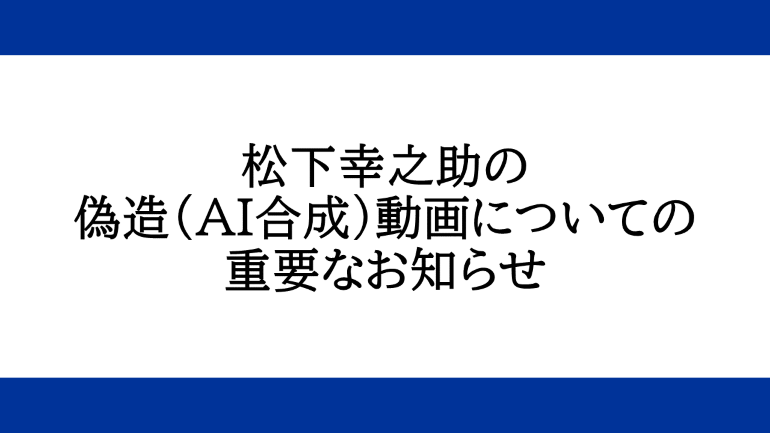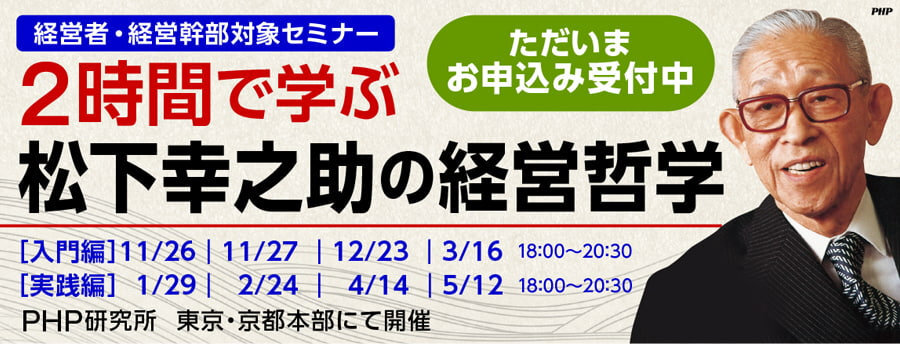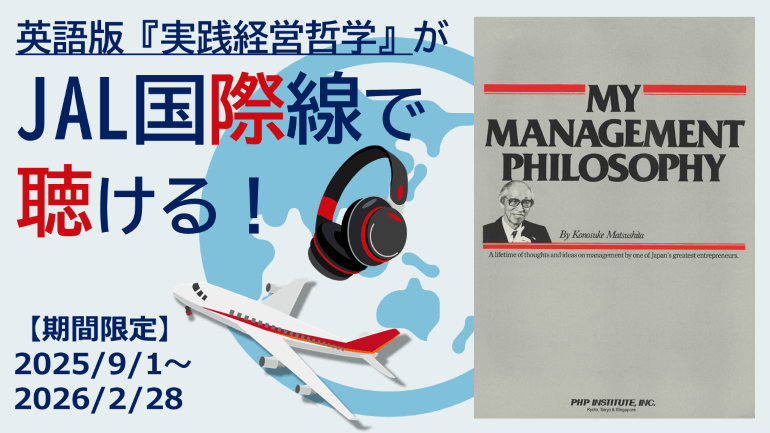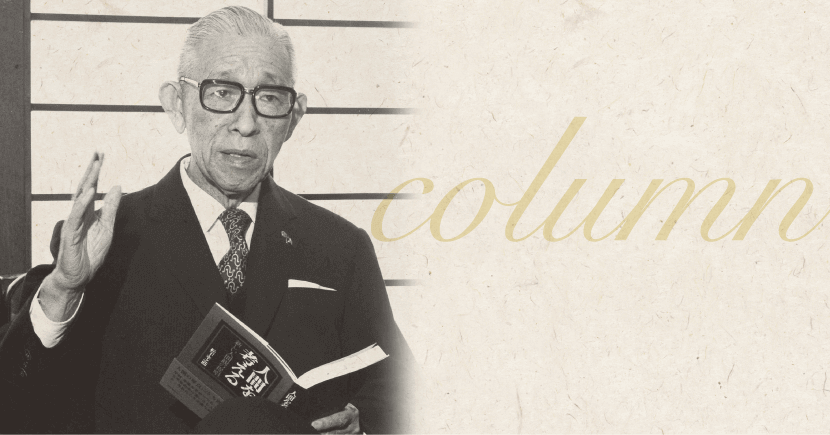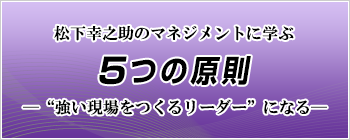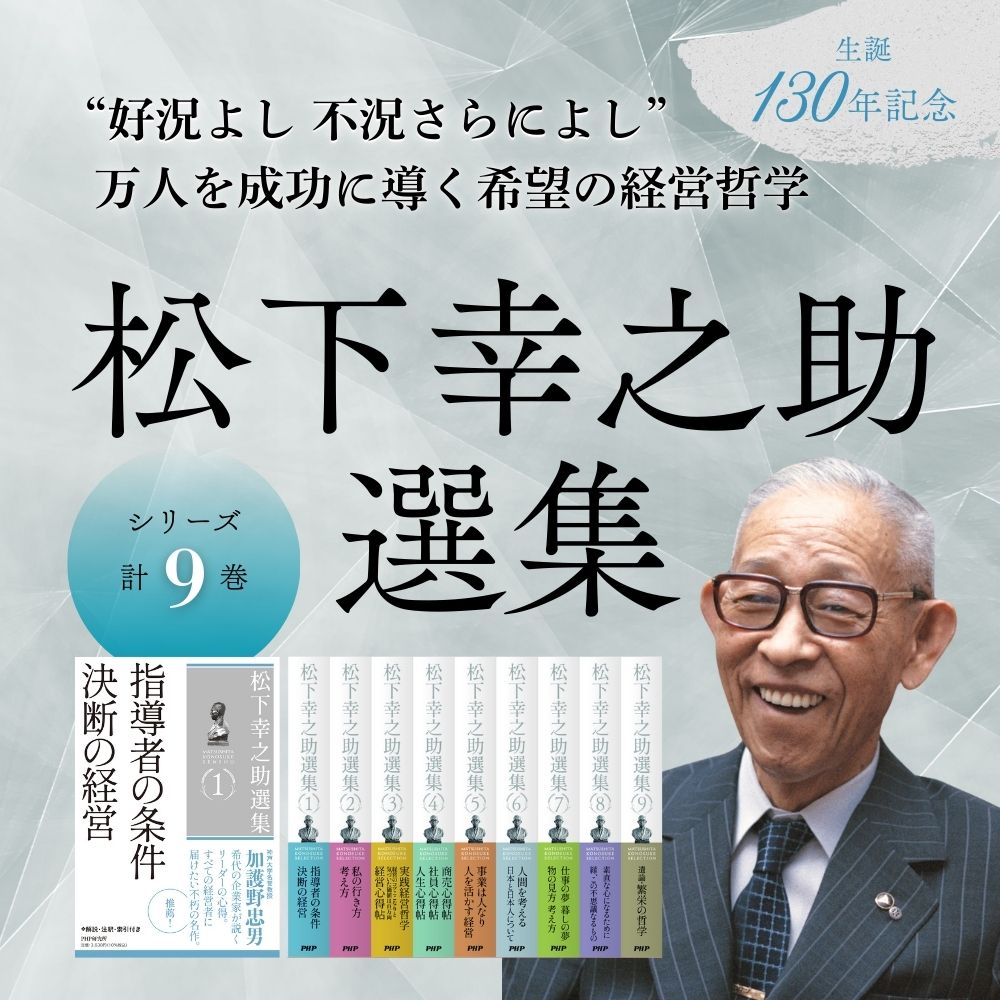ラジオの特許を無償で公開――経営の姿勢〈15〉
昭和初期のことである。特許魔といわれる発明家がいて、アメリカの特許を先に読み取っては日本で登録し、それを売るというようなことをしていた。ラジオの重要部分の特許権もその人が所有
血の出る首をくれ!――仕事を見る眼〈15〉
撹拌式や噴流式が開発され、電気洗濯機がようやく家庭に普及しようとしていたころ、松下電器はこの分野で他社に後れをとっていた。台所革命、家庭電化の、いわば尖兵を務める洗濯機で立ち
六十年間、ありがとう――人生断章〈15〉
一月十日。松下電器では毎年この日に経営方針発表会を行なっているが、とりわけ昭和五十三年のそれは、創業六十周年にあたることもあり、例年にも増して、意義深い日であった。 &nb
しるこ屋をやれ!――人を見る眼〈14〉
昭和三十年ごろのことである。新型コタツの発売に踏み切った直後に、誤って使用されれば不良が出る恐れがあるとの結論が出て、市場からの全数回収が決定された。 その回収に奔走して
真夜中の出社――情を添える〈14〉
PHP研究所がまだ真々庵にあった昭和三十年代のことである。幸之助は、非常に懇意にし、尊敬もしていた経営者の葬儀が翌日にあるということで、友人代表で読む弔辞の作成に取り組んでい
労組結成大会での祝辞――共存共栄への願い〈14〉
終戦直後の民主化の波のなか、各地で労働組合が生まれつつあった。昭和二十一年一月、松下電器においても労働組合が結成され、その結成大会が大阪中之島の中央公会堂で開かれた。 &n
天馬空を往く――繁栄への発想〈14〉
昭和四十年の大晦日、幸之助はNHKの「紅白歌合戦」の審査員席についていた。絢爛豪華な美しい舞台に、次々に歌手が登場して歌う。そんな歌手一人ひとりに拍手を送っていると、二時間四
名優・幸之助――経営の姿勢〈14〉
昭和三十一年ごろのこと、研究所の課長が手狭になった施設を拡充する決裁をもらうべく、幸之助を訪ねた。幸之助は自室で別の社員の報告を聞いていた。隣の秘書室で課長が待機するうち、幸
工場経営の基本――仕事を見る眼〈14〉
まだ戦後の混乱のさなかにあった昭和二十二年暮れのことである。たまたまその年は十二月二十五日の大正天皇祭をはさんで年末まで、飛び石で休日が続いていた。そこでいくつかの製造所から
質屋の通い帳――人生断章〈14〉
あるとき、幸之助宅の蔵の中から一束の古い書類が出てきた。配線工として勤めていた大阪電灯会社時代に会社からもらった十数枚の昇給辞令や、給与の明細書、退社したときに受けた退職金の
一年間何をしていたのか――人を見る眼〈13〉
入社して一年ほどで肋膜炎を患い、一カ月入院した青年社員が、社内新聞の編集担当部署に復職した。その一日目、青年はできあがったばかりの社内新聞を、幸之助のところへ届けるよう命じら
病と仲よく――情を添える〈13〉
ある幹部社員が病に倒れ、入院した。「一年くらいの療養が必要」「絶対安静」「面会謝絶」とつぎからつぎに出される医師からの宣告に、すっかり気落ちしてうつうつとベッドに身を横たえて